マタハラ研修は必須!厚生労働省の指針に沿った
進め方や効果的な教材など紹介

「マタハラ対策、何から始めればいいのか分からない」
「厚生労働省のガイドラインは読んだが、具体的な研修方法がイメージできない」
「社員の意識をどう変えればいいのか悩んでいる」
そんな人事・労務担当者の声が増えています。
マタニティハラスメント(マタハラ)は、企業の規模や業種に関係なく発生しうるリスクであり、すべての企業にマタハラ防止措置は義務化されています。
その一方で「何がマタハラに該当するのか」「どんな対策を実施すべきなのか」といった現場の戸惑いも根強く、放置すればトラブルや離職の原因にもなりかねないばかりでなく、採用面でも問題となりかねません。
また従来マタハラは「女性の問題」と思われていましたが、子育てをする男性の増加に伴い、父性への嫌がらせの意味であるパタニティハラスメントの問題でもあるという認識が高まっています。
そこで本記事では、研修教材を20年以上にわたって制作しているプロの立場から、マタハラ研修を実施する理由や方法、教材の選び方までを網羅的に解説します。
社員が「自分ごと」としてマタハラを理解し、安心して働ける職場環境を築くために、ぜひ本記事を参考にしてください。
なぜマタハラ研修は必要?法改正と経営リスクの視点から
職場でのマタハラは決して他人事ではありません。
調査によると、妊娠・出産を理由に不利益を感じた女性は約4人に1人にも上ります。
この数字は、マタハラが特別な職場だけの問題ではないことを物語っています。
★参考
独立行政法人 労働政策研究・研修機構「妊娠等を理由とする不利益取扱い及びセクシュアルハラスメントに関する 実態調査」
法改正による「義務化」で企業の責任が明確に
2015年(平成27年)1月の厚生労働省通達改正により、妊娠・出産・育児休業等を契機とした不利益取扱いは、原則として違法であることが明確化されました。
さらに、2017年(平成29年)男女雇用機会均等法、育児・介護休業法の法改正により、マタハラ防止措置(相談体制の整備や周知啓発等)が事業主に義務付けられました。
つまり、マタハラ防止に関する企業の責任は、法律によって明確に定められているのです。
法律で研修の実施自体が義務付けられているわけではありませんが、周知・啓発義務を確実に果たすうえで、研修は最も実効性の高い手段といえます。
ハラスメント対策の法的義務については下記の記事で詳しく解説していますので、ご覧ください。
[ハラスメント研修は義務化?罰則は?【2025年最新】企業の4つの必須措置と効果的な実施方法を解説]
無自覚な加害が生む深刻な経営リスク
マタハラは、必ずしも強い悪意からだけ生まれるものではありません。
行為者本人に悪気がなくても、無神経な発言や配慮に欠けた対応が結果的にハラスメントとなるケースが多く見られます。
マタハラの代表的なタイプは次の2つです。
| マタハラのタイプ | 例 |
|---|---|
| 制度等利用への嫌がらせ型 |
・産休や育休、時短勤務の取得を申請した際に「迷惑だ」「他の人が大変になる」と責める
・取得を諦めさせようとする |
| 状態への嫌がらせ型 |
・つわり等に対して「甘えている。病気じゃないんだから」「自己管理ができていない」と非難する ・業務を過剰に軽減し疎外感を与える |
「意図的な嫌がらせ」に加えて「無自覚に配慮を欠いた結果」によるマタハラも、当事者に深刻な影響を与え、次のような経営リスクを招きかねません。
- 優秀な人材の離職
- 労働基準監督署からの指導
- 訴訟リスクと企業イメージの悪化
- チーム内の信頼関係の悪化
だからこそ、単なるルールの周知ではなく、社員一人ひとりの意識改革が必要不可欠です。
マタハラ研修の実施は、法令遵守だけでなく、職場全体の信頼と安心を築く第一歩なのです。
子育てをする男性社員の増加にともないパタハラ対策も必要
従来、マタハラは女性特有の問題と考えられがちでしたが、近年は男性の育休取得が進み、取得率の公表も進む中で「パタニティハラスメント(パタハラ)」への理解も欠かせません。
たとえば、以下の発言は典型的なパタハラ事例です。
- 「戻っても席があるか分からないぞ」
- 「育休取るなんて出世を希望していないんですね」
- 「育休を取ったら評価が下がっても仕方ない」
これらは職場の心理的安全性を損ない、離職リスクや企業イメージ低下にも直結します。
つまりマタハラは女性だけの課題ではなく、男性社員も巻き込む組織全体の問題であり、企業は男女双方に配慮した研修と対策を進める必要があります。
厚生労働省のガイドラインが示す
マタハラ防止措置とは?
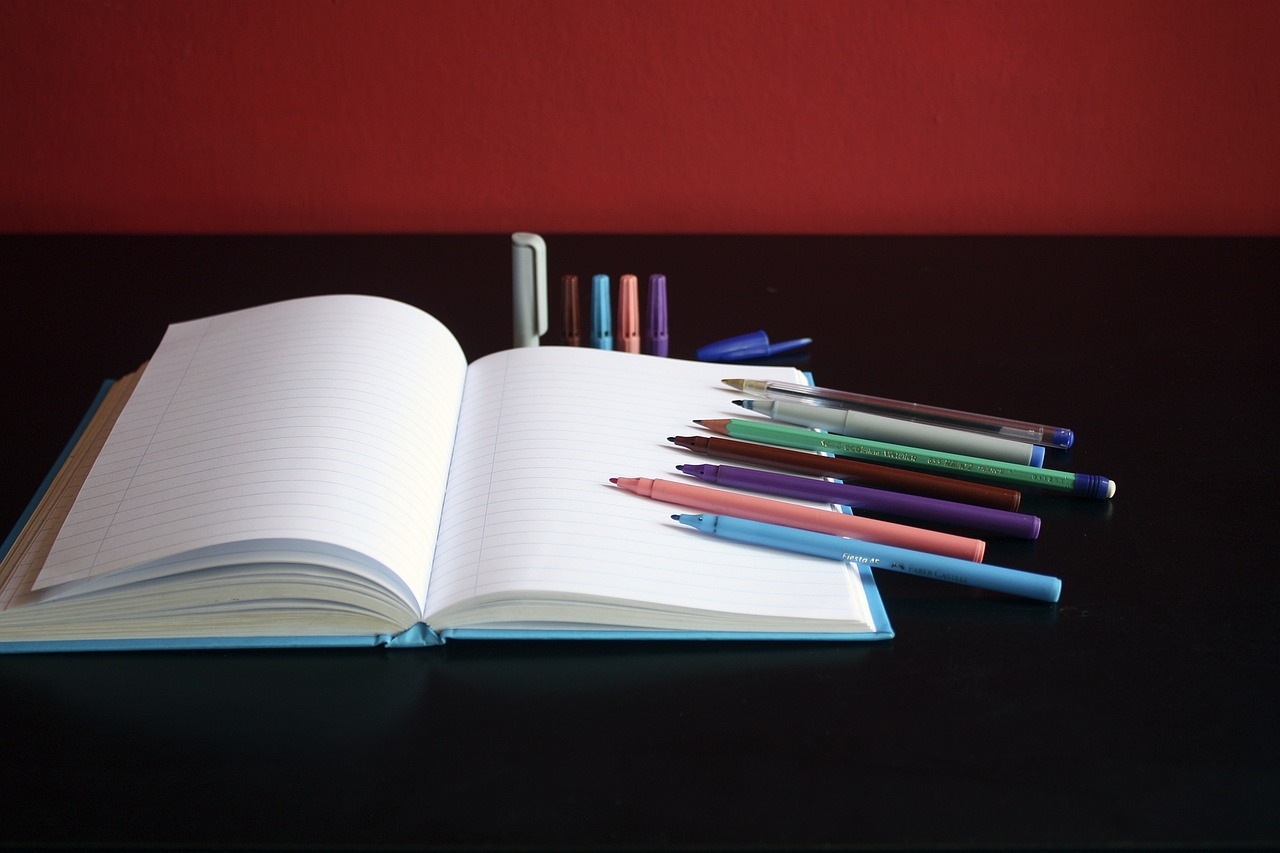
厚生労働省が示す「マタハラ防止措置」は、すべての企業に求められる基本方針です。このガイドライン(指針)には、事業主が実施すべき具体的な取り組みが定められています。
| 企業が講じるべき主な措置 | 内容 |
|---|---|
| 方針の明確化と周知徹底 | ・就業規則への規定
・ポスター掲示 ・社内報での発信など |
| 相談体制の整備 | ・相談窓口の設置
・担当者の指定 ・他のハラスメントの相談窓口との統合 |
| 適切な対応の実施 | ・迅速かつ適切な事実関係の確認
・事実関係の確認後の迅速な行為者対応 |
| ラスメントの原因や背景要因の解消 | ・業務体制など、必要な措置を講じる ・関係者への不利益取扱いの禁止の周知・啓発 |
マタハラ研修を実施して、全社員に正しい知識と意識を共有することは、最初の一歩として非常に効果的です。
マタハラ研修の基本設計は?効果を高める3つのポイント
マタハラ研修を形だけの施策に終わらせないためには「誰に」「何を」「どう伝えるか」が重要です
以下の3つの視点が、成功のカギを握ります。
ポイント1:全社員を対象に、定期的に実施すること
一度限りではなく、継続的な学習が意識の定着につながります。eラーニングなどを活用すれば、忙しい業務の合間でも受講できます。
人事異動や新入社員の入社などもあるため、定期的な実施によって組織全体の意識レベルを維持することが重要です。
ポイント2:管理職と一般社員で内容を分けること
管理職には部下への配慮や法的責任について、一般社員には協働の姿勢や言動への注意喚起を中心に構成しますまたマタハラ防止の対象について、事業主はもちろんのこと、上司や同僚の言動もその対象となりますので、一般職に向けた研修内容と、管理職に求められる研修内容を分ける必要があります。
同じ内容でも、それぞれの役割に応じた気づきを得られるような設計が効果的です。
また、近年増加している男性の育休取得に対するハラスメント(パタハラ)も研修に含めることが重要です。
「男のくせに育休なんて」といった言動も、ハラスメントに該当することに気を配りましょう。
ポイント3:事例・ドラマ形式で「自分ごと化」させること
リアルな事例を視覚的に体験することで、受講者はその場の感情や葛藤を疑似体験できます。
「知識として知っている」状態から「自分ごととして理解する」段階へと進めることができ、理解の定着や意識改革に直結します。
この臨場感のある設計が、マタハラ防止研修の効果を一段と高めます。
マタハラ研修の実施方法は?主なタイプを紹介

マタハラ研修の実施方法には、主に「eラーニング・映像教材型」「社内講師型」「外部講師型」の3つがあります。
それぞれの特徴を表で整理しました。
| eラーニング・映像教材 | 社内講師(資料自作) | 外部講師 | |
|---|---|---|---|
| コスト | 中~低 | 低 | 高 |
| 準備の手間 | 少ない | 多い | 中 |
| 専門性・正確性 | 高い(専門家監修) | 担当者の力量に左右される | 非常に高い |
| メリット | 時間・場所を選ばず実施可能。進捗管理もしやすい | 自社の状況に即した内容が作れる。コスト最小限 | 最新法改正に対応した専門的な内容。説得力がある |
| デメリット | 集中力維持に工夫が必要。一方通行になりやすい | 情報の正確性や最新性に不安。講師の力量に左右される | コスト・日程調整が必要。全社員に実施するには時間がかかる |
| おすすめの企業 | 全社員に効率的に実施したい企業 | 社内事情を反映させたい企業 | 質を最重視し予算に余裕がある企業 |
どの実施方法にも一長一短があります。自社の予算・体制・研修目的にあわせて最適な方法を選びましょう。
マタハラ研修の準備の手間とコストを解決する教材は?

マタハラ研修の準備に悩む担当者にとって、手軽に導入できる映像教材は心強い味方です。
アスパクリエイトの映像教材は、研修の効果と実施負担のバランスを両立させる3つの強みがあります。
強み1:ドラマ形式で「自分ごと化」しやすい
実際の職場でありがちなマタハラ事例をドラマ化することで、受講者が感情移入しやすく、理解が深まります。
「あるある」と感じる場面を通じて、無自覚な言動のリスクをリアルに体感でき、行動変容にもつながります。
強み2:セクハラ・パワハラ・マタハラを1本に集約
マタハラだけでなく、セクハラ・パワハラも含めて3種類のハラスメントをカバーできる教材も用意しており、複数回の研修実施が不要です。
マタハラだけでなく、セクハラ・パワハラも含めて3種類のハラスメントをカバーできる教材も用意しており、複数回の研修実施が不要です。
強み3:専門家監修+サンプル視聴で安心導入
専門家の監修により、現場の実態に沿った監修がされており、法的な正確性と信頼性を確保しています。
さらに、導入前にサンプル動画を視聴できるため「思っていた内容と違った」という失敗を防げる安心感があります。
これらの特徴が、限られたリソースの中で高品質な研修を実現する鍵となるのです。
まずはサンプル動画で、研修のイメージと教材のクオリティをご確認ください。
▼アスパクリエイトのサンプル動画を視聴する
サンプル動画:第2巻 マタハラ防止と管理職の役割(マタハラのない職場づくりのために)▼試写・購入・見積もりをご希望の方はこちらから
マタハラのない職場づくりのために 第2巻 マタハラ防止と管理職の役割マタハラ研修に関するよくある質問(FAQ)
マタハラ研修の実施を検討する中で、多くの担当者が共通して抱く疑問にお答えします。
Q1. 事例形式と解説中心のどちらが効果的ですか?
A. 両方のバランスが大切です。
事例(特にドラマ形式)は視覚的に理解しやすく「自分ごと」として捉えるきっかけになります。
一方で、法的根拠や対応策などは専門家による解説が不可欠です。
アスパクリエイトの教材は、事例→解説という流れで構成されており、感情と論理の両面から理解を深められます。
Q2. 研修の効果をどう測定すればよいですか?
A. 研修直後の理解度テストやアンケートが基本です。さらに、1〜3ヵ月後のフォローアップも有効です。
中長期的には、ハラスメント相談件数の推移、離職率、従業員満足度調査の結果も評価指標になります。
Q3. 厚生労働省の資料を使って研修を自作してもいいですか?
A. 可能です。厚生労働省はPDFやパワーポイント形式のハラスメント研修資料を無料公開しており、基礎研修は実施できます。
ただし、法改正への対応や受講者の関心を引く構成には高度な専門知識と多くの準備時間が必要です。
効率と質の両立を考えるなら、専門家監修の映像教材活用が現実的な選択肢といえるでしょう。
マタハラ対策の第一歩は、社員の「意識」を変えることから
マタハラ研修は、単なる法令対応ではなく、職場の風土を変える大切な取り組みです。
社員一人ひとりが「自分の言動が相手にどう影響するか」を意識できなければ、真の解決にはつながりません。
その実現をサポートしているのが、アスパクリエイトの映像教材 です。
- 20年以上の教材提供実績を持ち、官公庁や大手企業を含め幅広く導入されています。
- 受講者からは「法律でどのように決められているのかが良く分かった」「自分ごととして考えられた」といった高い評価が寄せられています。
- 専門家監修のもと、セクハラ・パワハラ・マタハラを一度に学べる効率的な教材も用意しています。
信頼と実績に裏打ちされた教材だからこそ、安心して導入いただけます。
まずはサンプル動画で内容をご確認いただき、効果をぜひ体感してください。お問い合わせやお見積もりは無料です。
▼アスパクリエイトのサンプル動画を視聴する
サンプル動画:第2巻 マタハラ防止と管理職の役割(マタハラのない職場づくりのために)▼試写・購入・見積もりをご希望の方はこちらから
マタハラのない職場づくりのために 第2巻 マタハラ防止と管理職の役割
