ビジネスと人権とは?企業ができる人権尊重のための取組も紹介
近年では「ビジネスと人権」というキーワードが世界的に注目されるようになりました。
日本においても2020年には政府からビジネスと人権に関する行動計画が公表されたことを受け、企業が従業員の人権を尊重する経営を求められています。
この記事では人権尊重の必要性や、人権尊重の取組の進め方について詳しく解説しています。
経営層やコンプライアンス担当の方はぜひ参考にしてみてください。
ビジネスと人権とは?
企業ができる人権尊重のための取組も紹介

2011年の国連人権理事会において「ビジネスと人権に関する指導原則」が合意されたことをきっかけに、企業活動における人権尊重が注目されるようになりました。
さらに2020年には日本でも「ビジネスと人権に関する行動計画」(NAP)が策定・公表され、2022年には「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」が明示されたため、多くの企業が人権尊重に積極的に取り組む方針を出すなどの取り組みを進めています。
この記事では「ビジネスと人権」についての解説と、企業の人権尊重の取り組みの進め方について詳しく紹介していきます。
「ビジネスと人権」とは?
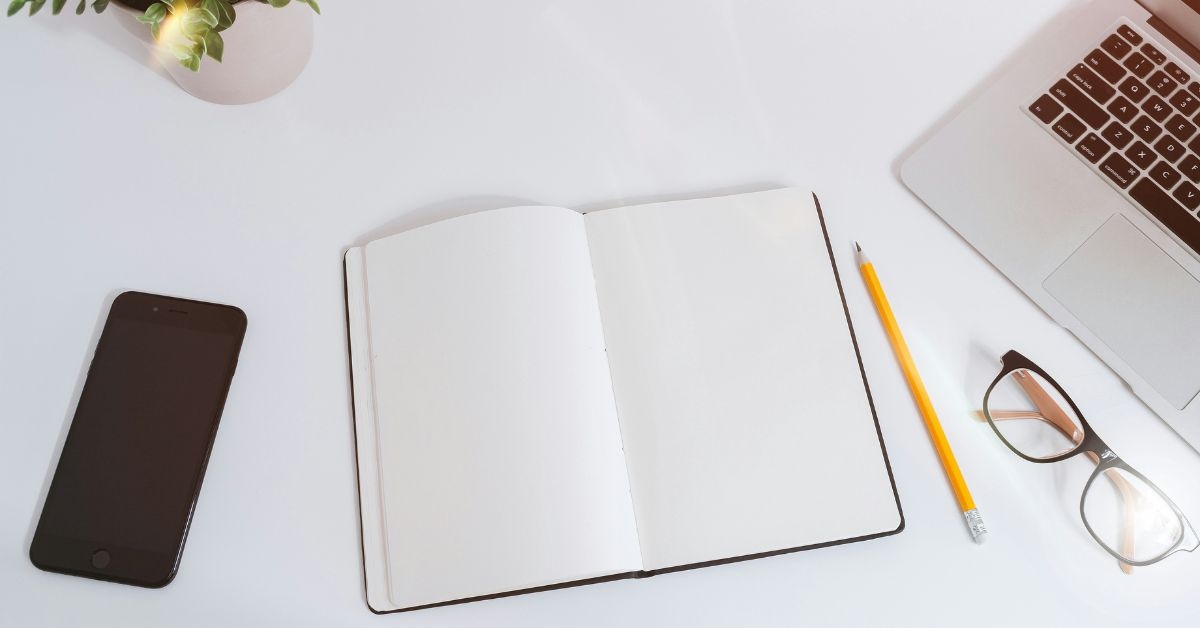
「ビジネスと人権」とは、企業が事業活動を通して影響を与える可能性のあるあらゆるステークホルダーの人権を尊重する概念のことを指しています。
企業は、この概念を発端とした人権尊重の取り組みとして人権侵害が行われていないかどうかを確認する「人権デュー・ディリジェンス」に継続的に取り組むなどの、人権尊重を確保し続けるための具体的な行動が求められています。
日本では人権尊重の取り組みが各企業で行われることで、ハラスメントの予防や長時間労働の見直しなどが期待でき、従業員一人ひとりの労働環境の改善に繋げることが期待されています。
なぜ企業活動における人権尊重が注目されているのか

ビジネス活動における人権問題は長年問題視されていましたが、グローバル化が進む中で人権侵害の実態が明らかになり注目を集めるようになりました。
第二次世界大戦後、平和や人権尊重を求める動きが高まっていきましたが、1990年代に入って、製品やサービスのサプライチェーンが国境を越えて広がっていく中で、人権侵害による問題が発生していったのがそもそもの発端でした。
労働力の不足を補うため、児童労働や従業員への長時間の過重労働を強いたり、資源を確保するために地域住民の健康を害する開発が行われるなど、侵害された人権の種類は多岐に渡ります。
このような状況を国連が認識し、さらに2015年のSDGs(持続可能な開発目標)の採択の後押しもあり、事業を通じて一人ひとりの人権を尊重する方針が打ち出されることとなりました。
もちろん日本も例外ではなく、現在では多くの企業では国連の方針や政府の発信に沿って従業員の人権を尊重する動きが活性化されているというわけです。
ビジネスと人権の三つの柱

国連が公表している「ビジネスと人権に関する指導原則」では、人権尊重の取り組みは「人権を保護する国家の義務」「人権を尊重する企業の責任」「救済へのアクセス」の3つの柱で構成されています。
ここからは、それぞれの柱の内容について詳しく解説していきます。
人権を保護する国家の義務
国家には、国民が第三者による人権侵害を受けることから国民を保護する義務があります。その例として、紛争地域の影響のある地域で活動する企業の人権尊重の支援のために、企業を指導することがあります。
またこの第三者には企業も含まれており、企業に対して労働者の人権を尊重することを義務付ける法律を制定・施行し、人権尊重しながら企業活動をするよう指導することなどが求められています。
人権を尊重する企業の責任
企業には、事業活動をどこで行っているかに関わらずすべての地域において、事業活動の中で関わることになるすべての人の人権を尊重する責任があります。
そのなかで、「人権方針の策定」「人権デュー・ディリジェンスの実施」「救済措置の構築」の3つに取り組むことが企業に求められています。
それぞれの取り組みについては、のちほど「企業の人権尊重への取り組み方法」にて詳しく解説していますので参考にしてください。
救済へのアクセス
人権侵害が生じた場合、国家は侵害を受けた対象を救済しなければなりません。
具体的には司法・行政・立法などの手段を使って対応することになります。
そのためには人権侵害を受けた人が救済を求めらえる仕組みを構築することが不可欠です。
問い合わせ窓口の設置や内部通報制度の拡充など、アクセス方法を人権侵害被害者がわかる状態にしておくように国家がサポートします。
また、グローバル企業においては多言語に対応できる窓口を設置するなど企業の実態に沿った対応が必要です。
この救済措置についてものちほど「企業の人権尊重への取り組み方法」にて紹介していきます。
企業の人権尊重への取り組み方法

ビジネスと人権の三つの柱のうちの一つである「人権を尊重する企業の責任」を果たす方法として、具体的な取り組み方法を3つ紹介していきます。
- 方針によるコミットメント
- 人権デュー・ディリジェンスの実施
- 救済措置
それぞれの内容について詳しく解説していきますので確認してみましょう。
方針によるコミットメント
企業では、人権を尊重する責任を果たすというコミットメントを策定して、公に示すことが求められています。そしてこの人権方針は、①企業のトップが承認していること、②社内外の専門家などから指導・アドバイスを受けていること、③従業員、取引先、製品やサービスに直接係るすべての関係者に対する人権配慮の期待を明記すること、④一般に公開されていて、従業員、取引先、出資者、その他の関係者に知らされていること、⑤企業全体の方針に反映されていること、が求められています。
人権デュー・ディリジェンスの実施
人権デュー・ディリジェンスとは、企業活動に関わる人権への負の影響を防止・軽減するための行動のことを言います。
この人権デュー・ディリジェンスを定期的に行い、その都度対処していくことで、人権侵害の被害を防止・軽減させていくことが狙いです。
特定した負の影響に対して対処したあとには、その措置が適切に機能しているかどうかまで確認することが求められます。
また人権デュー・ディリジェンスの取り組みについては、ウェブサイトなどで一般に公開していく必要があります。
救済措置
企業には、人権への悪影響が出たり、人権侵害の被害が出た場合に被害者を救済するために、苦情処理のメカニズムを整備することが求められています。
人権侵害を受けたステークホルダーが救済へのアクセスを確実にできるように、企業は仕組みを構築しなければなりません。その例としては、社内用の相談窓口はもちろんのこと、多言語対応の相談窓口の構築や、サプライヤー用のホットラインの設置なども挙げられています。

まとめ

経済のグローバル化が進む中で、企業活動のあらゆる側面での人権対応が注目されています。
自社内のハラスメントや長時間労働など、身近な労働問題も人権侵害の一つですが、サプライヤー企業の労働環境や原材料の生産プロセス、広告における映像表現など、様々な企業活動の中で人権方針に適切に対応していくことが、今企業に求められているのです。
企業に関わるあらゆるステークホルダーの人権を尊重することで、持続的に企業の発展が目指せるようになります。
改めて自社の人権問題に目を向け、現状のままで対応が十分なのかどうかを確認してみてはいかがでしょうか。

