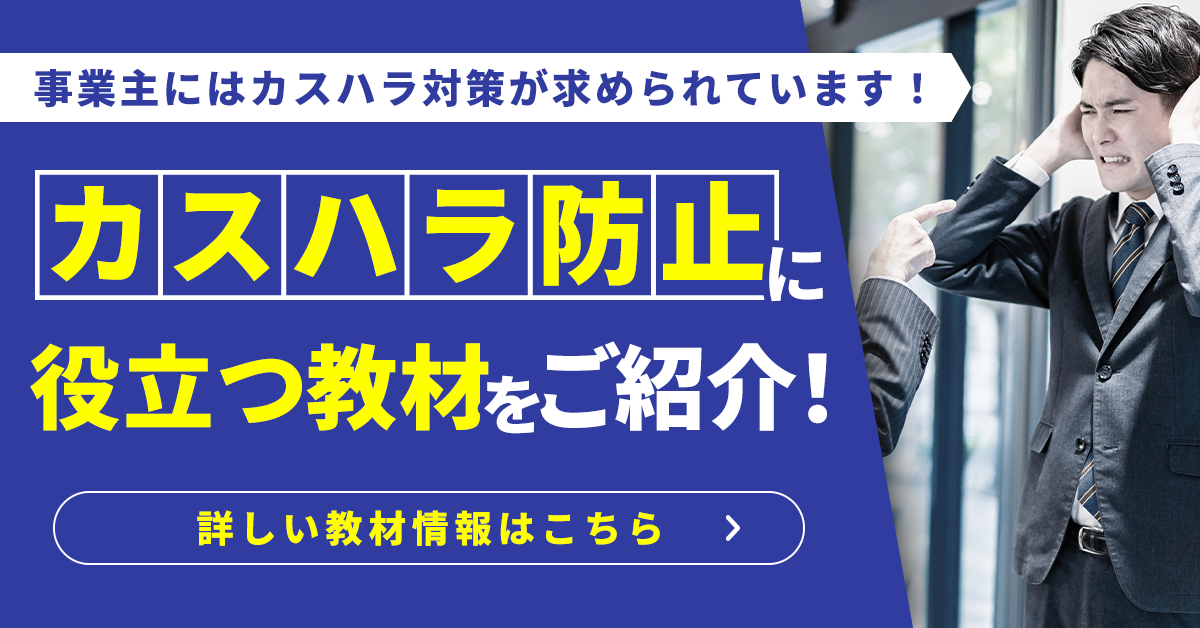カスハラの特徴から見る顧客対応
カスハラの特徴から見る顧客対応
|クレーム対策に効く4つの防止策と社内規定の作り方

「最近のお客様の態度が威圧的で、スタッフの精神的負担が増えています。」
「クレーム対応のマニュアルはあるものの、カスハラへの具体的な対処方法がわかりません。」
「社内規定を整備したいけれど、どこから手をつければいいのか...」
そう思う店長や人事担当者の方も多いのではないでしょうか。
実は、カスハラ対策で最も重要なのは、「予防」と「組織的な対応体制の構築」です。
適切な防止策と明確な社内規定を整備することで、スタッフを守りながら、健全な顧客関係を築くことができます。
この記事では、現場ですぐに活用できるカスハラの特徴と判断基準、実践的な4つの防止策、そして誰でも作成できる社内規定のテンプレートまでを詳しく解説していきます。
カスハラの特徴と見分け方|対応が必要な事例と判断基準

接客現場では日々様々なクレームが発生しますが、すべてがカスハラというわけではありません。
しかし、適切な対応のためには、通常のクレームとカスハラを明確に区別し、組織として適切に対処することが重要です。
ここでは、カスハラの具体的な特徴と判断基準について見ていきましょう。
カスハラとは?通常のクレームとの違いを理解する
カスタマーハラスメントとは、顧客による従業員への言動が、社会通念上の相当な範囲を超えて、精神的・肉体的な苦痛を与える行為を指します。
通常のクレームは、商品やサービスに対する正当な指摘や改善要求であり、建設的な対話が可能です。
一方、カスハラは、過度な要求や理不尽な言動を伴い、従業員の尊厳を傷つける行為となります。
カスハラの代表的な3つのパターンと事例
代表的なカスハラのパターンとして、「暴言・脅迫型」「執着型」「迷惑行為型」が挙げられます。
暴言・脅迫型は、従業員に対する大声での罵倒や、SNSでの誹謗中傷の示唆などが該当します。
執着型は、同じ内容を何度も繰り返し要求したり、長時間の拘束を強いたりする行為です。
迷惑行為型には、店舗内での撮影や録音を執拗に行う、他の顧客の迷惑となる行為を繰り返す、つきまといやセクハラなども含まれます。
カスハラかどうかの判断基準チェックリスト
カスハラの判断には、以下のような観点から状況を評価することが有効です。
一つは要求や主張に合理性があるか、つまりミスや落ち度に対する指摘なのか。二つ目に手段や態度・言動が妥当なものか。例えば従業員の人権・人格を否定するような言動ではなかったか。例えばSNSへのアップなどのプライバシーを侵害するような言動や、従業員を罵倒するような主張の仕方ではなかったか、などから判断することができます。
見逃してはいけない従業員のSOSサイン
カスハラを受けた従業員は、必ずしも明確に助けを求められるとは限りません。
そのため管理職が、被害を受けた従業員の表情や急な欠勤の増加、業務効率の低下など、微妙な変化に気づくことが重要です。
部下の変化に気づくためにも、管理職は定期的な面談や日常的なコミュニケーションを通じて、従業員の変化に敏感である必要があります。
カスハラ防止のための4つの具体策|現場ですぐに実践できる対応方法

カスハラへの対応は、事後対応だけでなく、予防的な取り組みが特に重要です。
ここでは、現場ですぐに実践できる具体的な防止策について解説していきます。
従業員の心理的安全性を確保する体制づくり
従業員が安心して働ける環境づくりの第一歩は、「誰もが声を上げやすい」雰囲気の醸成です。面倒なことを言わせないような雰囲気の職場では、被害を受けても相談できないためです。
自分で抱え込んでしまうことを防ぐために、管理職が定期的に個別面談を実施したり、匿名での報告システムの構築して周知することが効果的です。
また、カスハラを受けた際の対応手順を明確化し、組織として従業員をバックアップする姿勢を示すことが重要です。
クレーム対応の標準化とエスカレーションルール
社内規定の作成やクレーム対応の対応フローを作成して、どの段階で、誰がどのような対応を取るべきかを明確にします。
特に、現場担当者が一人で抱え込まないよう、上司や管理部門へのエスカレーション基準を具体的に定めることが重要です。
また、クレーム内容や対応の記録方法や報告ルートについても、統一した基準を設けましょう。
防犯カメラや記録による証拠保全の方法
カスハラ行為の証拠保全は、後の対応や再発防止に重要な役割を果たします。
防犯カメラの適切な設置と運用、やり取りの記録方法について、プライバシーに配慮しながら明確なルールを設定しましょう。
商談においても、必要に応じた録音ができるような体制構築も重要です。
警察や顧問弁護士との連携体制の構築
深刻なカスハラ事案に備え、警察や顧問弁護士との連携体制を事前に整備しておくことが重要です。
緊急時の連絡先リストの作成や、相談できる窓口の確保を行っておきましょう。
カスハラ対策の社内規定作成|必要な項目と運用のポイント

効果的なカスハラ対策には、明確な社内規定の存在が不可欠です。
ここでは、実効性のある社内規定の作成方法と運用のポイントについて解説します。
社内規定に盛り込むべき7つの必須項目
カスハラに関する社内規定には、①定義、②対応手順、③報告体制、④従業員保護措置、⑤記録方法、⑥研修制度、⑦見直し基準、を含める必要があります。
特に現場での判断基準については、正当なクレームをカスハラと取り違えたり、カスハラを抱え込むことの両方を防がなくてはならないため、その職場で起きたカスハラの具体例や、段階的な対応手順を明確に記載しておくことが重要です。
従業員への教育研修プログラムの設計方法
効果的な研修プログラムには、カスハラとはどのようなことを指すのか、カスハラの識別方法、カスハラにしない初期対応の実践、エスカレーションの判断基準などを含めておきます。
ロールプレイングを取り入れた実践的な研修や、定期的な事例共有会の実施も有効です。
実際の運用フローと記録の取り方
規定の運用には、現場での使いやすさを重視した具体的なフローチャートや記録フォーマットの整備が必要です。
また、記録の保管方法や活用方法についても明確なルールを設定しましょう。
定期的な見直しと改善のためのPDCAサイクル
社内規定は、定期的な見直しと更新が重要です。
半年に1回程度の頻度で、現場からのフィードバックを基に内容を見直し、必要な改善を行いましょう。
また、新しい事例や対応方法を随時取り入れ、より実効性の高い規定へと進化させていくことが大切です。
ハラスメント対策の研修用映像教材の依頼をするなら
研修用映像教材を依頼する際のポイント
カスハラを個人の問題とせず、組織全体で研修教材など活用して取り組む体制を整えることが重要です。
ここでは、研修用映像教材を依頼する際のポイントについて解説します。
明確な目的と対象の設定
- 新入社員向けの基礎知識か、管理職向けの実践的内容かを明確化
実際の事例やケーススタディの活用
- 具体的な事例を通じて学ぶことで理解を深める
分かりやすい視覚資料の使用
- 複雑な概念を図表やアニメーションで視覚化
これらのポイントを押さえて研修用映像教材を依頼することで、効果的かつ持続可能なカスハラやクレーム対応の教育プログラムを構築することができるでしょう。
株式会社アスパクリエイトがおすすめ
研修用映像教材を依頼するなら株式会社アスパクリエイトがおすすめです。
ここでは、株式会社アスパクリエイトの強みや他社比を3つ紹介します
| 1. 幅広い事業展開 | 研修用映像教材の企画・制作・販売、セミナー開催、スチール写真撮影、e-ラーニング事業など、研修業務全般にわたる多様なサービスを提供。 |
|---|---|
| 2. 豊富な取引実績 |
官公庁、地方自治体、大企業、団体、大学など、幅広い分野の顧客と取引している。
特に、中央省庁や都道府県庁、一部上場企業との取引実績は、同社の信頼性と専門性を示す。 |
| 3. 長年の経験 | 2002年の設立以来、20年以上にわたり事業を展開しており、特に研修用動画分野での豊富な経験と知見を蓄積。 |
このように効果的な顧客対応の教育を行うには、適切な研修用映像教材が不可欠です。
これらのポイントを踏まえて依頼することで、より効果的で持続可能な教育プログラムを実現できるでしょう。
気軽にご相談してみてください。