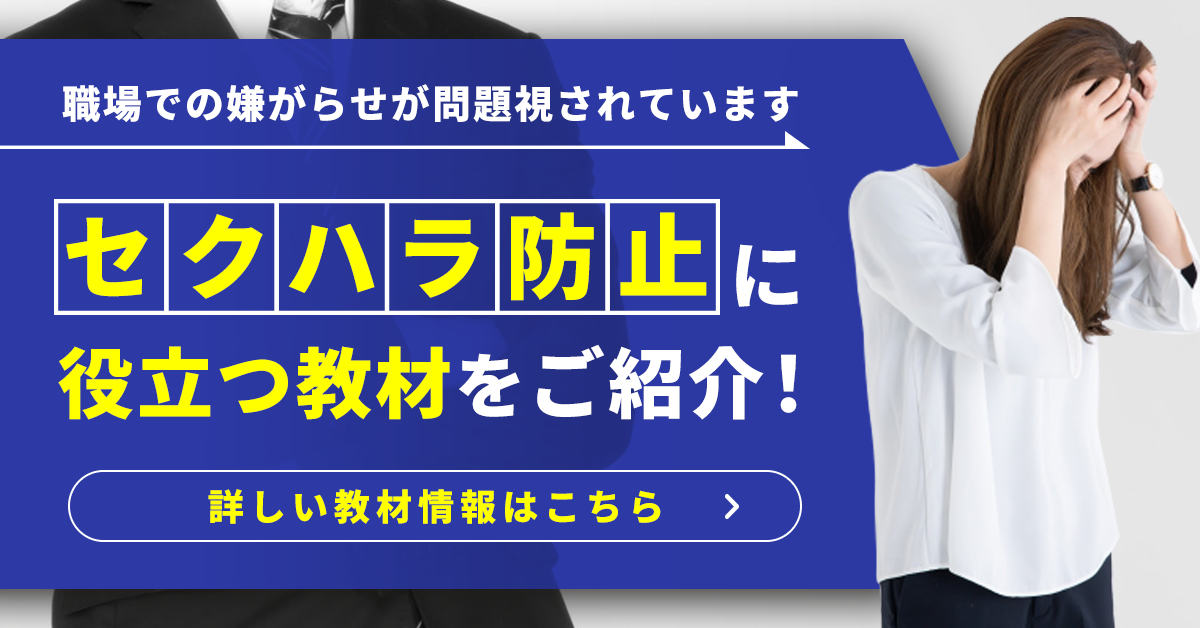セクハラ防止の第一歩は社内研修の徹底!
セクハラは職場で起こりやすいハラスメントの一つです。職場でのセクハラを防止するために対策を検討している人事担当者の方も多いのではないでしょうか。この記事ではセクハラ防止のための研修や会社としてできることについて解説しています。ぜひ参考にしてみてください。
セクハラ防止の第一歩は社内研修の徹底!
効果的な研修の内容やポイントも解説

職場でのセクハラは、被害者の精神的な被害が大きいこと、加害者への賠償請求や処分に伴うトラブルなど、多くの問題を引き起こす可能性の高い事案です。
また 表沙汰になった場合は、社外からの会社への著しいイメージの低下を招きます。
取引先への影響や新入社員の獲得への影響など、受ける影響の大きさは計り知れません。
そのため、セクハラを未然に防ぐべく対策を講じようと考えている人事担当者の方は多いのではないでしょうか。
この記事ではセクハラが起こりにくい会社にするためにできることや、研修実施の際のポイントなどについて詳しく解説していきます。
セクハラ防止研修を検討しているものの、実施方法や内容が決まらなくて困っているという方はぜひ参考にしてみてください。
セクハラとは

セクシュアルハラスメント(セクハラ)とは、職場で行われる労働者の意図に反した性的言動によりその労働者の就業環境が害される行為を指します。
ここでいう「労働者」ですが、確かに被害者は女性で加害者は男性というケースが圧倒的に多いのですが、男性が被害者の場合や同性同士のセクハラも存在しますし、性的少数者へのセクハラにも気を付けなければなりません。
セクハラかどうかを判断する基準として重要なのは、職務上の地位や関係性です。
被害者が「NO」と言えない関係性があることが、最もセクハラの被害を重くするのがその理由です。
そして次に、被害者がどの程度不快に感じているかという、労働者本人の不快感の程度が重視されます。
その際に、被害者が女性であれば、その職場の平均的な女性労働者の感じ方が基準となります。
そもそもパワハラとは異なり、セクハラは業務と関係なく生じることが多いため、特に管理職など、ポジションのある人は注意が必要です。
セクハラ防止のために企業ができること

セクハラが起こらない会社をつくるために、会社が取り組むべきことはいくつもあります。
その中でも主な手立てとして挙げられるのは以下の3点です。
- セクハラに対する会社の方針の明確化
- セクハラを相談しやすい窓口を設置
- セクハラ防止研修の実施
それぞれの内容について詳しく解説していきます。
セクハラに対する会社の方針の明確化
セクハラ事案が発生した場合の会社としての対応方法についてを明文化し、管理監督者への周知徹底を行いましょう。
万が一生じた場合の処分についてもあらかじめ規程を設け、全社に周知しておくと、会社がきちんと取り組む意思をもっていることが伝わりやすくなります。
ハラスメントを認めないというトップのメッセージを発信するなど厳格な姿勢を見せることも、社員が安心して仕事に取り組みやすい社風づくりに繋がります。
セクハラを相談しやすい窓口を設置
セクハラの当事者になったり、セクハラの場面に遭遇した際に、社員が気軽に相談できる窓口を設置しましょう。
社内への相談窓口設置で大切なことは、男性・女性両方の相談員を配置することです。
特にセクハラは同性同士でなければ相談しにくいと感じる人も多くいるので、相談員の性別に注意が必要です。相談員の育成には、定期的な専門研修の受講が有効です。
また、社内では相談しづらいと感じる方もいるので、社外窓口を用意しておくのもおすすめです。
そして相談した秘密が守られること、きちんと相談に対応されその経過が相談者に報告されること、相談者への二次被害が無いことなどが分かれば、社員が働くうえで安心感や会社への信用にも繋がります。
セクハラ防止研修の実施
今どきセクハラ?と思う人もいるかもしれませんが、コミュニケーションの手段や感覚が変わることで、昔はあり得なかったセクハラが報告されてきています。そのためその時々に併せてアップデートした内容で研修を続けていく必要があります。
ハラスメントの防止措置を取るのは企業の義務となっており、その対策の一つとしてセクハラ研修を導入している企業は多くあります。
研修を実施することは、会社としてセクハラ対策が重要な問題と考えているという姿勢を示す機会にもなりますので、セクハラ防止研修は積極的に導入すると良いでしょう。
セクハラ防止研修に取り入れるべきコンテンツ

セクハラ防止のために社内研修を実施するのは効果的な対策です。
どこにポイントを置けばいいか分からないという研修担当者の方もいらっしゃるのではないでしょうか。
ここからは、研修コンテンツとしてぜひ取り入れてほしい以下の3つのポイントについて解説します。
- セクハラの定義を周知
- 最近のセクハラ事案の事例共有
- セクハラに遭遇した時の対応方法
それぞれの項目について詳しく解説していきますので、参考にしてみてください。
セクハラの定義を周知
研修ではセクハラの定義を周知し、社員全体の認識を統一することが大切です。
セクハラという言葉を知らない社員はいないかと思いますが、何がセクハラにあたるのかという認識は人によって異なるケースが多々あります。加えて世代間で感覚が異なる場合もあります。
しばしば間違われることですが、自分がセクハラをしたつもりはないという「意図」が無いことは、セクハラの加害をしなかったことにはなりません。
こうした認識のずれにより、加害者側にはセクハラだという認識がなく、被害者側がセクハラだとして訴えているという事案は珍しくありません。
正しい知識を持つことと、新しい情報にアップデートすることで、こうした無自覚なセクハラ事案を防止する対策となります。
最近のセクハラ事案の事例共有
研修コンテンツの中には、最近起きているセクハラの事例を取り入れるのがおすすめです。
セクハラの事例は時代と共に変化してきていますので、最近どんなことが起きているのかを紹介しておくことはとても重要です。
その際、知識をわかりやすく伝える研修を組み立てられたとしても、受講者が自分事として研修内容を受け止めて受講しなければ効果は半減してしまいます。
自分の身近に起こり得るセクハラのケースを具体的に紹介することで、自分も当事者になり得ることを理解してもらえるでしょう。
例えば、事例ドラマの動画を利用するなど、共有の方法を映像にすると、よりリアルなイメージが持てるので効果的です。
言葉や行動を可視化することで伝わりやすくなる上記憶に残るため、研修実施による効果も高まります。
セクハラに遭遇した時の対応方法
万が一職場でセクハラの当事者になったり、セクハラと思われる場面に遭遇した場合の対応方法について周知しておきましょう。
被害については、まず内部もしくは外部の相談窓口を利用を促すのが一般的です。
安全に相談できる場所があるとわかっていれば、被害者は一人で抱え込まずに済み、精神的な苦痛を和らげることに繋がります。
人事上のダメージや報復を受けることがないなど、安心して話ができる場所であるということをアピールするのも大切です。
特にセクハラ当事者の場合には、心の整理がつかずに自分から相談しづらくて悩んでしまう方も少なくありません。
職場での出来事となれば、その後の自分の立場などを心配して声を出しづらいという方もいるでしょう。
会社は公正公平な立場で適切に対応することを、社員全体に伝えておくことが大切です。
効果的なセクハラ防止研修を実施するためのポイント

ここからは社内でセクハラ防止研修を行う際に効果を高められる3つのポイントについて紹介していきます。
- 社員全員を対象として行う
- 定期的に実施する
- 常に最新情報にアップデートさせる
それぞれの詳しい内容について解説していきますので、研修を行う際にはぜひ取り入れてみてください。
社員全員を対象として行う
セクハラ防止研修を行う際には、全員を受講対象者として、案内するようにしましょう。
社員全員へ研修を実施することで、自分が被害を受けた時その言動がセクハラに相当することが理解できると共に、組織全体のセクハラに対する意識の向上が期待できます。
また、社員一人ひとりが正しい知識を身につけておくことで、セクハラ事案自体の発生を予防することにも繋がるでしょう。
会社全体の人権意識を高めることに繋がるため、対象を全員にすることを検討してみてください。
それに加えて、管理職には自分が加害者になる可能性が高いこと、相談を受ける可能性があることのため、別途研修を行う必要があります。
定期的に実施する
研修実施直後は受講した社員自身の意識が高まっているため、セクハラの発生を予防する効果が期待できます。
しかし、一度行うだけでは時間が経つに連れて効果が薄くなってしまいがちです。
具体的な頻度としては、一年に一度を目安に定期的に実施するのがおすすめです。
継続的に実施することで受講者の理解も深まり、組織全体のパワハラが起こりにくい風土の醸成にも繋がります。
管理職向けの研修についても同様です。
常に最新情報にアップデートさせる
研修を定期的に実施することが効果的だとお伝えしましたが、実施の際には内容の見直しを都度行うことも忘れないようにしましょう。
特にハラスメントに関する法令の変更等があれば、研修内容に変更が生じる可能性があります。
人事担当者は社会のセクハラに対する動きや情報もキャッチし、研修に反映させていくことが大切です。
まとめ

セクハラは職場での日常のコミュニケーションの中でも起こる可能性のある身近な問題です。
社員一人ひとりに正しい知識を身につけさせるなど、会社全体でセクハラ発生を予防するための対策を講じることはとても重要です。
セクハラ事案が起こると、当事者はもちろん、同じ職場にいる社員の職場環境も損なわれます。
風通しの良い働きやすい労働環境を守るためにも、セクハラが起こらない組織づくりを目指しましょう。