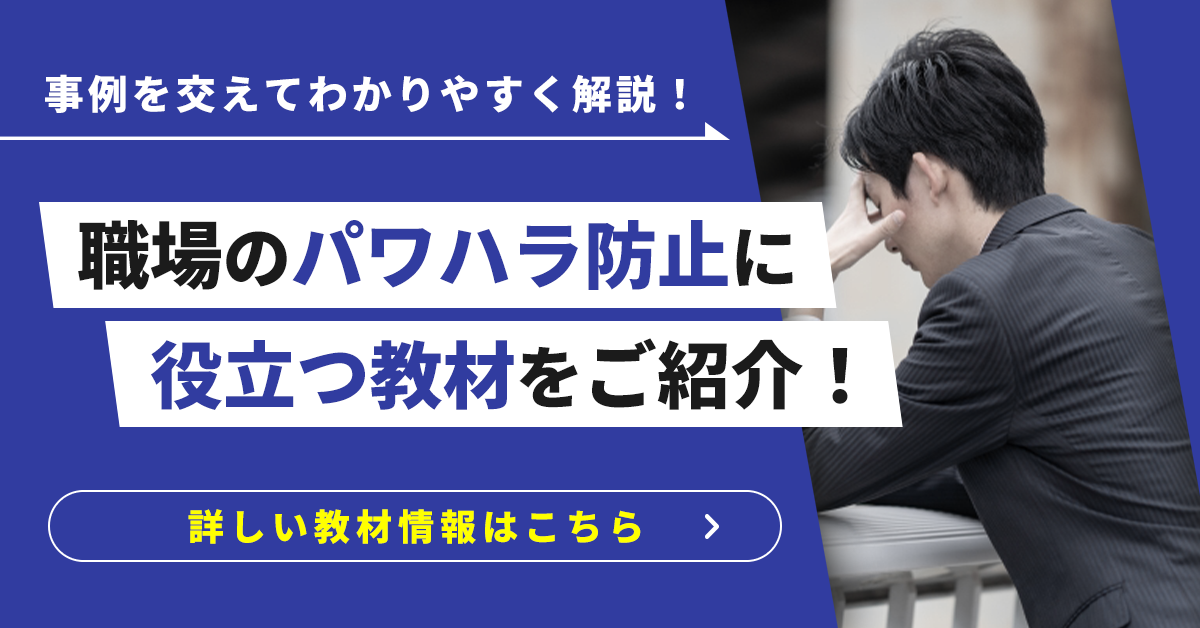パワハラ防止には教育が重要!
パワハラ防止のための施策について頭を悩ませている人事担当者の方も多いのではないでしょうか。
企業の成長のためには優秀な人材が必要ですが、人材を育てる過程には上司や先輩社員からの指導が欠かせません。
正しいパワハラの知識を身につける教育を行うことで健全な指導が行われる環境が作れます。
この記事では、パワハラ防止のための社内教育や組織づくりについて解説していきます。
パワハラ防止には教育が重要!
パワハラが起こりにくい組織についても解説

パワハラ防止のために社内での教育を実践している企業は多くあります。
職場ではより良い企業に成長していくためにも上司から部下への指導による育成は不可欠ですが、近年ではその指導を部下からパワハラだと言われるケースも増えてきました。
パワハラが起こると、被害者となった社員はもちろんですが加害者となった社員もダメージを受けることになります。
人材育成に熱意がある人ほど、気付かぬうちにパワハラに相当する指導をしていたということも少なくありません。
その逆に、パワハラの判断ポイントを受け手が不快に思えばパワハラだと思っている人も多く、必要な指導が伝わらないという問題も起きています。
上司と部下が健全な関係で、適切な指導が行われ、指導と認識されることがパワハラの訴えの対策として大切です。
この記事では、ハラスメントが起こりにくい教育のポイントや組織の作り方のコツについて解説しています。
ぜひ働きやすい職場づくりの参考にしてみてください。
パワハラを防ぐ教育とは

現在では法改正により、どの企業においてもパワハラの防止措置を講じることが義務付けられています。
そもそもパワハラが発生する職場は健康的に働けるとはいえないため、社員の休退職が多いなど生産性が低くなり、企業にとっても好ましくない職場である可能性があります。
そうした背景から、パワハラ対策への取り組みは必然となってきています。
パワハラ防止研修を行うほかに職場の人間関係を円滑化する研修や、チームビルディングを通して良好な人間関係の構築を図るなど、教育の方法は企業によって様々です。
ハラスメント防止教育は現代の会社経営においては不可欠なものだと言えるでしょう。
パワハラとは

厚生労働省の定義によるとパワハラとは以下の三つの要素を全て満たした言動のことを指します。
- 職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性(優越的な関係)を背景としている
- 業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える
- 労働者の職場環境を悪化させる行為
また、パワハラとされる主な言動には以下の6類型があります。
- 身体的な攻撃
- 精神的な攻撃
- 人間関係からの切り離し
- 過大な要求
- 過小な要求
- 個の侵害
ここからは、それぞれの内容について解説していきます。
身体的な攻撃
上司が指導の場で、部下に暴行を加える行為は、上司には優越的な立場があり、業務の適正な範囲とはいえず、部下は不快に思うと考えられるためパワハラとなります。
指導の場において部下の頭を叩く、蹴り飛ばすなどは、叩くことや蹴ることが指導に必要であることの説明ができません。
例え部下に酷いミスがあったとしても、手を挙げるのはNGです。
精神的な攻撃
上司が部下を指導する場合に、部下の人権・人格を侵害するような言葉で、精神的に傷つけることもパワハラにあたります。
例えば、他の社員がいる前で長時間叱責したり、CCメールで部署の全員に知らせる形でその中の一人を指導することもこの種類のパワハラに該当します。
そもそも指導である以上、そのやり方で部下の能力が上がること、或いは部下の仕事が進むことを目指さなくてはなりません。
指導の本来の目的を忘れないように心がけましょう。
人間関係からの切り離し
職場の中で、一人だけ蚊帳の外に置くような対応を取るのもパワハラに該当します。
この場合、同僚同士の場合であっても、大人数の方が優位であると考えられるため、業務上必要な連絡を回さないなどによって業務に支障が生じる環境であることはパワハラとなります。
「職場」の意味として、業務上つながる場所は出張先、移動の車の中、部署の忘年会などの宴会の場も含みますので、1人だけに部署の歓送迎会の日程を教えないというような行為はこの類型にあてはまります。
過大な要求
到底終えることのできない業務量や、明らかに本人の能力では難しいと思われる業務を指示することを指します。
新人で仕事のやり方が分からないのに、大量の仕事を押し付けるようなケースが相当します。
上司は可能だと判断しても、実際の部下の力量に対して不当な難易度である場合もあるので、特に少し高めの目標を与えるつもりの場合は、その程度についてきちんと精査しておく必要があります。
過小な要求
例えば管理職に雑用を命じることや、運転手に草むしりを命じるなどの行為が相当します。
こうした行為は、業務を命じられた社員がやりがいを感じられなくなり、自信を失うことに繋がる可能性があります。
そのため業務の適正な範囲を超えていないかという視点から見ると、本来の仕事のスキルが求められないような仕事をさせたり、力量に合った仕事をさせないことで就業の意欲を奪うことにつながり、パワハラであることになります。
個の侵害
個人のプライバシーや性格について侵害したり、否定するのもパワハラの一つとされています。
例えば仕事がなかなか覚えられない社員に対して、「親の育て方が悪いからだ」などといった、過去のことや生い立ち、家族に対する悪口はNGです。
仕事に対しての指導は、あくまで業務上のことのみで表現し、本人の努力で変えられないことに触れないようにしましょう。
他に、他人のスマートフォンを黙って 見ることや、性的少数者であることをアウティングする(本人の了解を得ずに口外する)などもこの類型にあてはまります。
パワハラにならない指導のコツ

言動がパワハラなのか指導なのかの判断は難しい場合があります。
指導した相手の相手の捉え方が重要なポイントになってくるので、使う言葉や表現の仕方、伝え方に工夫を加えることが大切です。
誤解を生むことのないような指導をするコツを紹介していきますので、ぜひ参考にしてみてください。
不適切な表現を使わない
同じことを伝えたとしても、表現一つで相手の受け取り方は変わってきます。
例えば家庭を持つ女性社員に指導をする場面があった時、「子育てで忙しいからって仕事に支障をきたさないように」などといった表現は不適切です。
子育て中であることを知っておくことが、就業時間の配慮に必要な情報である場合はありますが、業務内容の指導の仕方としては適切ではありません。
家庭や家族のことは業務上に必要な内容ではありませんので、むやみにプライバシーには触れないようにしましょう。
具体的に指導する
部下指導の際、上司の指示自体が曖昧であることがあります。
部下のスキルや経験によっては、段取りや必要な情報を細かく与える必要がある場合もあると思います。それを「よろしく頼む」とまとめて伝えてしまうことはないでしょうか。
それで分かる部下であれば良いですが、往々にして上司が考えていたゴールとは、幾つか、或いはたくさんのズレが生じてしまいます。
その結果上司はキレて部下を恫喝するようなパワハラにつながるとすれば、元々上司の指示の仕方に丁寧さが足りなかったことも原因かもしれません。
「1言えば10理解してくれる部下によろしく頼む」で良いとしても、1言って1理解する部下に対しては、段取りを細分化してそれぞれの指示と、それが理解されているかの確認が必要となるでしょう。
人格を否定する言い方をしない
ミスの多い部下、報告しない部下、協調性の無い部下など、上司も人間ですので「この人はいつも・・・」と思うこともあるかもしれませんが、叱責する際に「あなたはいつも××だ」というような言い方をすると、その部下は上司から常にネガティブに見られていると覆うでしょう。
こうした叱責の仕方は精神的な攻撃に当たりますし、部下はそもそも上司からの評価が低いと感じて、やる気を出せないというマイナスのループに陥ってしまいます。
上司には部下を育成する職務もありますので、部下に期待を持つことを表明したいものです。
相手の発言を否定しない
指導する相手の言い分はしっかり受け止めましょう。
目につくことや気になることだけを一方的に伝えるのはNGです。
指導の対象となる言動を取るまでに本人なりの意図や背景があるケースもあります。
指導の前後に、きちんと相手の言い分をヒアリングするようにしましょう。
この時、決して否定せずにまずは受け止める姿勢を見せることが大切です。
パワハラ防止に繋がる組織体制のコツ

パワハラが起こりにくい企業の風土を醸成するためには、社員全体への教育と併せて、組織風土や相談体制を整えておくことが必要です。
そもそもパワハラが起きにくい組織風土とは、風通しが良いことが上げられます。そうした職場では誰もが必要な事を言い合えるため、何かあれば本人に直接、或いは周囲に相談することが可能です。
また相談しやすい組織体制を構築し、相談に適切に対応することが理解されれば、パワハラの抑止や再発防止に期待できます。
ここからは、相談体制について具体的に紹介していきます。
パワハラ遭遇時の相談窓口を周知
実際にパワハラの当事者になったり、パワハラと思われる場面に遭遇した時に、どんな相談窓口に行けばよいのかについて周知しておきましょう。
社員全体が相談しやすい環境であることを分かりやすく知らせておくことで、組織が本気でパワハラ対策に取り組んでいることが伝わり、抑止に繋がることが期待できます。
周知の方法としては、社員向けのサイトへの案内、ハラスメントに関する研修資料やeラーニング教材に相談窓口一覧を載せる、定期的にメール等で案内を入れておくなどの方法があります。
案内は一度で終わらせるのではなく、機会を見て繰り返し行うことが大切です。
内部相談員の充実
社内の相談員として、パワハラだけでなくセクハラ、マタハラについても知識を持った相談員を配置しておくことが重要です。
それぞれのハラスメントは単独で起きる場合とは限らず、複合的に起きる場合もあります。
できる限り女性・男性それぞれ用意しておけると良いでしょう。
性別によって相談しにくいと感じてしまうケースもあります。
気軽に相談できないとなると、せっかく内部相談の窓口を設置していても効果が出にくくなるでしょう。
誰でも気軽に相談できる場所として認知してもらうことが大切です。
外部相談窓口の設置
相談者の中には、社内の人には相談しづらいと感じている人も少なくありません。
社内の人間関係に関することなので、相談相手が社内の人では本人に漏れてしまうのではないか、自分の評価が下がるのではないか、報復を受けるのではないか、など不安を感じてしまうことがあるためです。
そのような方でも安心して相談できるよう、外部に相談窓口を設置しておくのも有効な手段の一つです。
会社の人ではない第三者であれば公平に話を聞いてもらえることで相談しやすいので、相談者としては安心です。
まとめ

パワハラに該当することなく適切に指導をするためには、社員への教育が必要です。
正しい知識や気を付けるべきポイントを共有することで、パワハラ事案の発生を抑止することができます。
社員全員が安心して仕事に集中できる環境を作るためにも、パワハラ防止研修を徹底して行うのがおすすめです。
生産性向上の面からも、ぜひ取り入れてみてください。