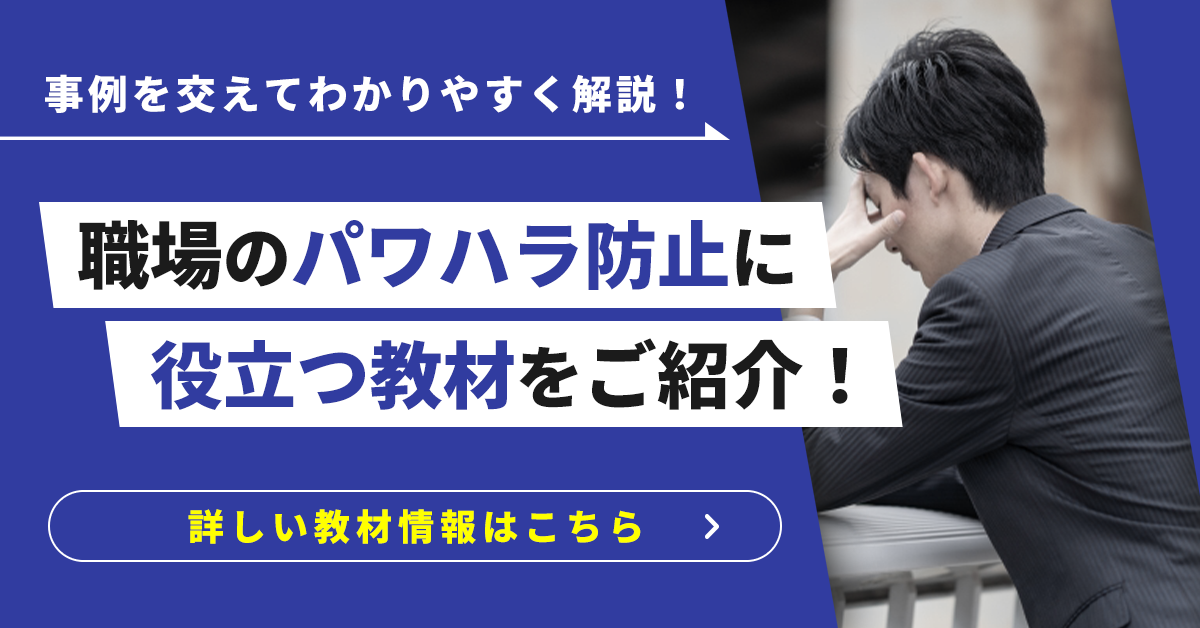パワハラ研修には動画が最適!
社内でパワハラ研修を行うのであれば動画の活用がおすすめです。この記事では、研修動画によって得られる効果や動画制作の流れについてご紹介しています。パワハラ研修を企画している担当者の方はぜひ参考にしてみてください。
パワハラ研修には動画が最適!
効果がある理由や動画制作の流れも解説

パワハラ防止のために研修を導入している企業は年々増加しています。具体的な研修内容や手法は企業によって様々です。自社にとって効果的な研修を行うために内容や手法を検討している研修担当者の方も多いのではないでしょうか。
この記事ではパワハラ研修には動画がおすすめな理由や、動画制作をする際の手順について解説しています。ぜひ参考にしてみてください。
パワハラ研修の目的

パワハラ研修を実施する目的は、研修を受講することで社員全体のモラルを向上させてパワハラが起こらない職場環境を作ることです。
パワハラという言葉は理解していても、具体的にパワハラとは何を指しているのかについては認識が人によって異なっている可能性が高いと言えるでしょう。
そのため、社員一人ひとりで過度に意識しすぎていたり、意識が薄すぎるといった差が生まれるといった状況がどの会社にも起こっているのではないでしょうか。
社員全体の認識を統一することで、管理職は適切な部下指導を行い、同僚同士が適切な距離感で円滑にコミュニケーションを取りやすくなることが期待できます。
せっかく社内でパワハラ研修を実施するのであれば、目的を達成できる効果的な方法を検討して行うことが大切です。
パワハラ研修に動画が最適な理由5選

結論から言うと、パワハラ研修を効果的に行うのであれば動画を活用するのがおすすめです。
直接対面で研修を行うなど様々な手法がありますが、動画だからこそ得られるメリットが多く存在します。
ここからはパワハラ研修を行うのに動画を活用するのが最適な理由を5つ解説していきます。
繰り返し受講できる
動画を活用することで、受講者が自分のタイミングで何度でも視聴できるようになります。
社員全体で揃えて研修を実施すれば、パワハラへの全体への意識の向上に期待できます。
しかし、研修を受講してすぐに知識が活用されるとは限りません。
例えば初めて部下の育成に問題を感じた時や、パワハラの疑いがある場面に遭遇した時など、研修の知識が必要となるタイミングは人によって異なります。
社員が各自で必要な時にその都度視聴できるのは、動画ならではのメリットと言えるでしょう。
当事者意識を高められる
パワハラ研修を受講してもらう上で大切なのが、受講者に当事者意識をもってもらうということです。
一般的な講演者による講義形式での研修でも知識をインプットする効果はありますが、一方的に話を聞くことが多くなり、どこか他人事として話を聞いてしまいがちです。
動画での研修であれば、パワハラの再現ドラマを視聴してもらうなど、工夫の幅が広がります。
実際の職場のイメージに近い映像であれば、パワハラ事案を自分事として捉えて能動的に受講する期待が持てます。
そして動画はスライドや講演だけよりも記憶に残るため、高い研修効果が見込めるでしょう。
研修の質を均一化できる
研修を動画化することで、同じコンテンツを同じクオリティで受講者全員に届けられます。
研修を担当者が直接行うタイプの研修では、どうしても研修ごとにニュアンスや表現の仕方といった細かい部分の統一は難しくなります。
ちょっとしたニュアンスが変わるだけで、受講者に与える印象が異なってしまうケースが出てくるのが懸念点です。
研修を動画化することで社内全員が同じ研修を受講することになるので、知識の偏りなく認識を統一できるのは大きなメリットと言えるでしょう。
研修を受講しやすい
対面の研修の場合、いざ研修実施の準備を進めていく際に研修運営者を悩ませるのが日程の調整です。
同じ会社であっても部署によって繁忙期が異なります。
全員が受講できる余裕があるタイミングを見定めつつ、研修効果が高い時期を判断して日程を予定するのは難易度が高いものです。
また、無事に開催できたとしても欠席者の対応フローなど検討すべきことは多くあります。
欠席者の対応として一般的なのは当日使用した資料の共有ですが、それだけでは効果が薄くなるのが難点です。
動画研修であれば、これらの懸念点を解消できます。
動画コンテンツを活用すれば、全員が会場で顔を合わせて研修実施する必要がなくなるため、移動時間を削った最小限の時間で行うことが可能になります。
忙しい社員でも業務の調整がしやすくなるため、安心して前向きに受講できるでしょう。
また、万が一欠席者が出ても、動画を共有するだけで同じ研修を受講してもらえます。
全員が研修を受講しやすくなるのは動画研修ならではの強みです。
研修コストが削減できる
一般的に対面での研修を実施する場合には、ある程度のコストがかかります。
研修会場費や社員の移動費、アウトソーシングする場合にはその分の料金が必要です。
社員の人数が多ければ多いほど、会場費と移動費だけでもかなりの金額がかかるでしょう。
動画研修であれば自分のPCさえあればどこでも受講可能です。
それぞれのオフィスで受けてもらえるので、会場費・移動費共にコストを削減することができます。テレワーク中の受講も可能となります。
動画研修により最低限の費用での研修運用ができるのは嬉しいポイントです。
研修動画の制作プロセス

研修動画を制作する時に発生する一般的なプロセスについて解説していきます。
アウトソーシングする場合にも社内で制作する場合にも大まかな流れは同じです。
それぞれの工程を確認してみましょう。
研修の目的を検討
まずどのような立場、階層に対しての研修なのか、どのような結果を目的とするのかを確認します。例えば全社員に対して、パワハラとはどのようなことか再確認することを目的とする、といったことです。
その上で研修の対象者や実施予定日時、欠席者の対応フローなど大まかに決めていきましょう。
研修の案内はどのように行うかなど、できるだけ具体的にイメージを持ちながら進めていけると細かな業務まで洗い出しやすくなります。じっくり時間をかけてチーム全体で考えていきましょう。
また、業務内容を基にして研修実施までのスケジュールも可視化しておけると準備が進めやすくなるのでおすすめです。
研修動画の内容を検討する
研修動画の内容や形式について検討します。
一般的にはパワハラの定義やパワハラに該当する行為などの知識を身につけるパートや、リアルなイメージを持ってもらうために事例ドラマを視聴するパートなどを設けるのが効果的です。事例ドラマを活用する場合、市販の教材データを購入する方法もあります。
研修受講者の集中力を途切れさせないように、内容や構成、長さは効果的な方法を検討しながらしっかりと組み立てていきましょう。
動画の台本作成
内容や構成が固まったら、続いて動画撮影をするための台本を作成します。
台本は設計図であり、どんな表現で伝わるかを考える上でもとても重要なものです。
研修動画全体の時間も台本次第で変わってくるので、必要な時間を最適な時間内に収められるように調整しながら作り上げましょう。
映っている場面や言葉のそれぞれによって、受講者に伝えられる内容やニュアンスが変わってくるので、複数のメンバーでチェックを重ね、修正していくのがポイントです。
動画の撮影・編集
動画の撮影と編集を行います。
台本に沿って素材となる動画を撮影します。できるだけ一度で素材を撮りきれるように、予備の素材となる映像も複数撮影しておくのがおすすめです。
また、その場で映像や音声の入り具合も都度確認しておくことで、失敗を防ぐことが可能となります。
撮影が終わったら動画を編集していきます。慣れるまでは膨大な時間がかかる可能性がありますので、スケジュールに余裕を持たせて、担当者の業務を整理しておけると良いでしょう。
まとめ

パワハラ研修を行うのであれば、研修動画を活用するのが効果的です。
研修動画の制作は自社で行うことも可能ですが、記事の中で解説してきたように制作するためには膨大な手間と時間がかかるため、本来の業務にも支障が出る可能性が高いでしょう。
クオリティやコストパフォーマンスを考えると動画制作は外部企業に依頼するのがおすすめです。
ご紹介してきたように研修動画にはメリットが豊富にあるので、パワハラ研修を企画するのであれば導入を検討してみてはいかがでしょうか。