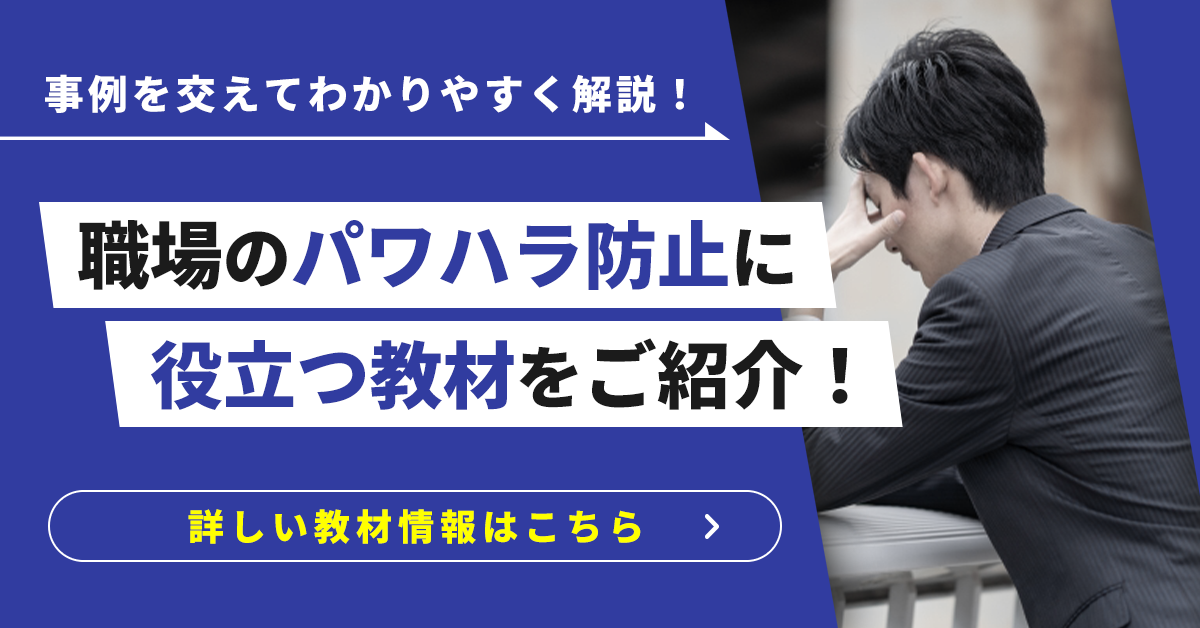パワハラ研修はどうやって実施すればいい?
社内でパワハラ事案が発生することで、企業は大きなダメージを受けてしまいます。パワハラが起こりにくい風土を醸成するためにも、パワハラ研修の実施を任せられているという研修担当者の方も多いのではないでしょうか。
この記事では、パワハラ研修の内容や準備について詳しく紹介しています。
ぜひ企画立案する際の参考にしてみてください。
パワハラ研修はどうやって実施すればいい?
研修内容や資料についても解説

パワハラが社会問題として認識されるようになり、どの企業でも社内でのパワハラをなくすために防止策を講じています。その防止策の一つとしてよく取り入れられているのが、パワハラに関する研修の実施です。
社員全体の認識をそろえるためにも効果的な方法ですが、研修の企画立案・実施の担当者の方は研修内容や準備の進め方で頭を悩ませることも多いのではないでしょうか。
この記事では、研修担当者の方に向けてパワハラ研修の目的や内容・資料の準備などについて詳しく解説しています。
ぜひ社内で実施するための参考にしてみてください。
パワハラとは

様々なハラスメントがあると言われているなか、パワーハラスメント、セクシュアルハラスメント、マタニティハラスメントの3つは事業主への防止対策が法制化されていますが、その中でも最も報告件数も多く事案になりやすいのがパワーハラスメント(パワハラ)です。
パワハラとは、職場での優越的な関係を背景として、業務の必要かつ相当な範囲を超えた言動により、就業環境を害すること、この3つの条件が全て揃うことが該当します。
この「優位性」とは役職による上下関係のみを示しているわけではありません。
一般的には上司から部下に対して行われるイメージが強くありますが、先輩や後輩といった関係性や同僚同士の間柄でもパワハラとして認められるケースもあります。
誰もが加害者にも被害者にもなる可能性を持っているため、パワハラ研修は管理職に対してはもちろんのこと、全社員を対象として行うのが良いでしょう。
パワハラ研修の目的

パワハラ研修を行うことでパワハラが起こりにくい風土の醸成を図ることが目的です。パワハラという言葉は社員全員が知っていても、「何がパワハラに当たるのか」については認識がばらばらということがよくあります。
そのため、パワハラと言われたくないために指導を控えるなど、過度に意識しすぎてしまい部下指導に支障が出てしまう可能性があります。
逆に、パワハラへの認識が足りていないばかりに、相手のためを思っての言動が無意識のうちにパワハラになってしまうということも十分にあり得ることです。
社員全体の認識を統一しておくことで、「これはパワハラ」「これはパワハラではない」という基準が相互に理解できている状態になるため、パワハラが起こりにくい職場を作ることができます。
社員が身体的にも精神的にも安心して仕事に打ち込めるようになり、生産性の高い職場を作ることができるでしょう。
パワハラ研修実施のメリット

パワハラ研修を実施することは会社や社員にとって様々なメリットがあります。
ここからは数あるメリットのうちの以下の3つについて詳しく解説していきます。
- 退職防止に繋がる
- 優秀な人材の確保
- メンタルヘルスの向上
それでは、それぞれの内容について確認していきましょう。
退職防止に繋がる
これまでは転職に対するハードルを高く感じる人が多い傾向にありましたが、昨今では転職するのが当たり前といった風潮が感じられるようになってきました。
転職を検討するきっかけになる大きな理由の一つとして職場の人間関係が挙げられます。退職する社員が直接パワハラに関わっていなかったとしても、パワハラが起こっている職場は決して居心地の良いものではありません。
研修実施により職場でのパワハラを抑止することで、働きやすく生産性のあがる職場が実現できれば、退職防止にも効果があると言えるでしょう。
優秀な人材の確保
職場のハラスメントが深刻化していることを受け、2020年6月の法改正によりパワハラ防止措置が事業主に義務付けられました。その後の2022年の更なる法改正にて中小企業も対象となったことで、日本の企業は全てパワハラ防止措置を行うことが求められています。
定期的にパワハラ研修を実施していることは、この義務を十分に遂行しているというアピールにも繋がり企業イメージを高める効果があると言えるでしょう。
またパワハラ研修によりパワハラが起こりにくい風土を醸成することができれば、入社の応募者数を確保することに繋がります。
特に新卒については、待遇面はもちろんのこと社風を重視する傾向にあります。心身共に健康に楽しく働ける会社を探しているという就活生は少なくありません。働きやすい職場環境をつくることで、応募者の母集団形成にも好影響が出てくるでしょう。
応募者が多ければ多いほど活躍を期待できる人材が集まるので、将来的な会社の発展にも期待できます。
またパワハラの加害者は、懲戒処分の対象になることがあります。パワハラ自体が減少すれば、処分される人も減るため、そうした人材を失うリスクも減っていくことでしょう。
メンタルヘルスの向上
職場のハラスメントは、パワハラ、セクハラなどが、労働災害の要因としても認定されており、精神的な健康を害することが分かっています。
そのため適切な研修が行われ、どのような言動が職場のハラスメントとなるのか、不適切な言動であるのかが職場で共有されれば、ハラスメントとなる言動は減少して、それに伴い社員のメンタルヘルス不調が少なくなっていくことでしょう。
パワハラ研修の内容

法改正によりパワハラ防止措置は義務化されたと紹介しましたが、パワハラ研修の内容については定められていません。
企業によって行っている研修の内容は様々です。
ここでは、研修の目的を達成できる効果的な研修を実施するために、ぜひ取り入れたい内容について解説していきます。
- パワハラの定義
- パワハラの事例紹介
- 振り返り
ぜひ研修の企画立案の参考にしてみてください。
パワハラの定義
研修では、厚生労働省が定めているパワハラの定義を改めて紹介しましょう。
パワハラという言葉は知っていても、その具体的な内容については理解できていない人がほとんどです。
高圧的な態度や指導がパワハラにあたるというような、ぼんやりしたイメージで捉えていることが社員の大部分である可能性が高いでしょう。
必要な指導をしている中で、少し声を荒げたことがパワハラとまではいえない場合があります。それとは逆に、穏やかな口調であっても人権侵害となるような内容でパワハラとなるケースもあるでしょう。
改めてパワハラに該当する言動を確認することで、社員全体の認識を統一するとともに、会社の取り組みへの真剣さを伝えることに繋がります。
パワハラの事例紹介
パワハラの定義を理解するために、その内容を事例として考えてみる必要があります。
「職場での優越的な関係」と「業務の必要かつ相当な範囲を超えた言動」は、字面ではとても分かりにくいものです。
そのため研修のコンテンツの中に、実際のパワハラの事例紹介を入れるのがおすすめです。
受講者が自らの日常の会話や周囲との関わり方と照らし合わせることが出来れば、自分事として研修内容を受け止めることに期待できます。
具体的には、リアリティのある映像による再現ドラマで伝えるのが効果的です。配布資料やスライドなどを使って言葉で伝えるよりも、自分を投影しやすく身近に感じてもらえるでしょう。
振り返り
職場での自分自身の言動を振り返る時間を設けてみましょう。
一人で振り返ることも大切ですが、他者と一緒に振り返りを行うことで客観的な視点を取り入れることができます。
大前提としてパワハラを意図的に行っているという方は少ないものです。場合によっては相手のためと思っている場合すらあります。
無意識のうちに他者に対して取っている言動がパワハラに該当するかどうかは、第三者と共に振り返ることでより確認しやすくなります。研修受講後の行動変化に期待できるコンテンツなので、ぜひ取り入れてみてください。
研修資料の準備

研修を実施するためには資料の準備が不可欠です。
準備するべき資料の種類や準備の仕方について解説しているので、確認してみましょう。
研修資料の種類
研修資料として準備が必要になるのは以下の2つです。
・配布資料
・投影資料
それぞれの資料について詳しく紹介していきます。
配布資料
配布資料とは、受講者が研修内容を理解しやすくなるように用意しておく資料です。
受講者が研修の振り返りに用いることができるので、要点や確実に伝えたいことを整理して記載しておきましょう。
ただし、記載する情報が多すぎると研修を受講する意味が薄くなってしまいます。資料を読むだけの研修にならないよう、注意が必要です。
投影資料
投影資料とは、研修を進めていくために用意しておく資料を指します。
スライドなどを活用する場合には、研修の話者が進めやすいようにポイントに絞って作成しましょう。
また、スライドと話者による講演だけでは受講者も飽きやすくなります。
動画資料を含めるなどで、メリハリのある研修資料を用意するのがおすすめです。
資料準備の方法
資料の準備には研修担当者が自作する方法と、外部の資料を活用する方法の2種類があります。
どちらにもメリット・デメリットがあるので、自社の状況に合わせて最適な方法で準備を進めましょう。
社内作成
研修資料は研修担当者が自作することも可能です。社員が自ら行うことでコストをかけずに研修の準備を進めることができます。
しかし、研修資料準備には膨大な時間がかかり、本来の業務への支障が出る可能性が高いです。
特に動画資料を用意する場合には撮影・編集が必要になるのでより一層時間がかかります。
また、研修には専門的知識も必要になるので、研修内容に誤りがないよう研修実施前に社内で十分にチェックすることが必要です。
外部資料の活用
研修をサービスとして提供している企業に研修資料作成を依頼する方法もあります。
社内作成よりもコストはかかりますが、専門性とクオリティの高い資料を用意できるのは大きなメリットです。
研修担当者の負担の大幅な軽減に繋がるので、研修運営に集中できる環境を整えられます。
まとめ

パワハラ研修を定期的に実施することで職場のパワハラ抑止に繋がります。
社員が安心安全を感じながらのびのびと勤務できるようになるため、より成果に繋がる仕事に期待できるでしょう。
より効果の高い研修を行おうとすれば、その分準備が増え、研修運営側への負担は大きくなります。
クオリティの高い研修と運営側の負担軽減のどちらも実現するためには、研修資料については外部委託するのがおすすめです。
ぜひ研修を実施する際には外部への依頼も検討してみてください。