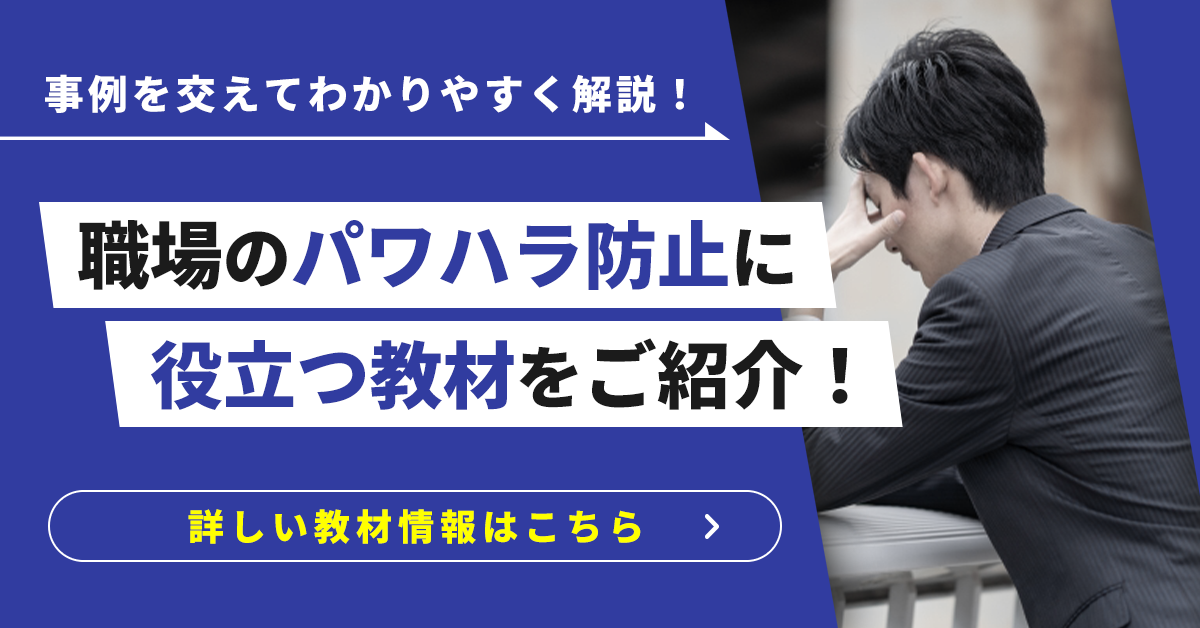ハラスメント加害者には慎重に対応を!
ハラスメント事案が起きた時に事業主は被害者・加害者どちらにも適切な対応をすることが求められます。特に加害者への対応は個人を尊重しながらも再発防止策を講じなければならないので慎重に行うことが大切です。本記事では、対応の留意点や再発防止のための研修内容について解説していきます。
ハラスメント加害者には慎重に対応を!
対応時の留意点や研修ついても解説

どれだけ力を入れて防止策を講じていたとしても、残念ながらハラスメント事案が生じてしまう可能性はどの企業にもあります。
ハラスメント事案発生時には、センシティブな案件だからこそ被害者・加害者どちらにも慎重に対応することが大切です。また、加害者へは処分と同時に再発防止に繋げるための研修が必要になります。
本記事では、パワハラが発生した時の対応方法や再発防止のための研修について解説しています。留意すべきポイントについても紹介してるので、人事担当者の方はぜひ参考にしてみてください。
パワハラ加害者に見られる主な特徴

パワハラ事案にて加害者となる人にはいくつか共通して持っている特徴があります。
ここでは主な3つの共通点に絞って紹介していきますので、パワハラ加害者特有の特徴を見ていきましょう。
古い感覚のままでいる
ハラスメント全般について言えることですが、そもそも「ハラスメント」についての目が厳しくなってきたのは比較的最近のことです。
部下に対して鼓舞の意味を込めて強い口調や態度で叱責することが当たり前に行われていた時代も確かにありました。
その経験があったからこそ自分が成長できたと感じている人は、同じようなことを部下に行う可能性が高くなります。
とはいえ、同じ時代で成長した人でも、現代の流れや風潮を正しく察知して順応している人は大勢います。古い価値観に固執したまま部下や後輩とのかかわりを続けているという点がハラスメント加害者に比較的多く見られる特徴です。
プレイヤーとしては優秀
パワハラ事案が起こる要因の一つとして、加害者がプレイヤーとしては優秀な人であるということが挙げられます。
トップセールスであった人などの、常に先頭を走っている認識の優秀な管理職からすると、自分のやり方がベストかつ全てである場合があります。そうすると部下のやり方に必要以上に口を挟んだり、部下の人権や人格を否定するような言動での指導となることがあります。
技術は見て学ぶものという信念
技術は教えてもらうものでは無く見て学ぶもので、後輩や部下が積極的にそうした姿勢を取るべきだという主張する人もおり、このパターンの上司たちは部下に指導しないタイプのパワハラ加害者になりがちです。
管理職の職務の一つが部下指導ですので、指導を行わないこともパワハラに繋がる可能性があります。
パワハラ発覚時の事業主がとるべき対応

パワハラ問題が社内で生じていることが発覚した場合、当然事業主はその事案に対応しなければなりません。
具体的な対応の手順について、事案発生から被害者への相談対応、再発防止に至るまでをフェーズごとに解説していきます。
パワハラが発覚するきっかけ
パワハラが発覚するのは主に社内もしくは社外に設置されている相談窓口への通報、社内から担当部署や上司への通報などが主なタイミングとなります。
他にも社内へのアンケートやストレスチェック後の面談など、個人の不安や心配事を伝えらえる場面で打ち明けられるケースもあります。
被害者本人から直接相談がある場合もあれば、被害者を心配した第三者から相談があるケースも。
まず大切なことは、パワハラかなと思ったとき、どこに相談できるのかを周知しておくこと。そして相談しやすい風土の醸成や相談できる仕組み・きっかけをつくっておくことがパワハラを放置しないことに繋がります。
いずれにしてもこのような相談があがってきたら、迅速に対応しなければなりません。
被害者への対応
被害者から直接相談を受ける場合を想定してみましょう。
相談を受ける場合に大切なのは、被害者本人に寄添った対応をすることと、二次被害とならないように気を付けて対応することです。
被害者に寄添った対応をすることとして、まず被害者が今の事態をどのように収束したいかがあります。被害が止まるだけで良いのか、会社として厳しく処分して欲しいのかなど、希望に幅がある可能性があります。
パワハラは、日常的に接する上司からの被害であることが多いので、被害者(部下)は報復を恐れて、誰が相談したか分からないようにして欲しいと求められることもあります。
また二次被害とは、相談の場などで被害者に対して「あなたに落ち度があったせいだ」「そんなことは気にするほどのことではない」などと、被害者を責めたり、被害を軽く扱うような言動を指します。
またパワハラは、被害者の感じ方だけでは決められないことが多いので、その点でも注意が必要です。

パワハラの訴えとその後の対応
パワハラ問題の難しいところは、暴行・暴言などの言動もある一方で、上司と部下のコミュニケーション・ギャップを部下がパワハラと思い込むようなグレーな言動まで、態様にかなりの幅があることです。
こうした事案を全て処分ありきでジャッジすると、多くの事案が“パワハラ”として処分されますが、実は第三者が間に入って両者の話を聞いてみると、こじれたコミュニケーションを第三者が仲介することで元に戻れるケースもあります。
前述の通り“加害者”には優秀な管理職も多いので、うまく解決できれば、組織は優秀な人材を失わないで済むというメリットもあります。
部下はパワハラと感じてもパワハラではないケースも少なくないとはいえ、指導が上手くいっていないことには変わりないので、パワハラと訴えてくるところには、何らかの問題があるとして対応していくことが重要です。
上司が陥りやすいパワハラの勘違い
そもそもパワハラとは何か。「優越的な関係を背景とした言動」、「業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動」、「労働者の就業環境が害される」の3点をすべて満たす言動と定義されています。
上司から部下へのパワハラで考えますと、そもそも上司は職位が上で「優越的な関係が背景」にあり、部下がパワハラだと感じており「就業環境が害されている」ので、その言動が「業務上必要かつ相当な範囲を超えている」かどうかがポイントとなります。
パワハラで勘違いされがちなのが、別室に呼んでの叱責だったとしても、部下を見下すような人権を侵害する叱り方だったり、指導内容が具体的ではなく指導としては不適切であったり、ただ懲罰的なだけで指導とは言えない言動だったりするケースです。
上司にヒアリングをすれば「部下の為を思って言った」「適切に指導している」と言いがちですが、その言動が本当に指導に相当するのかがポイントなので、大声は出していないとか、人前で叱責していない、ことを満たしていれば良いわけではないのです。
再発防止の研修
パワハラ加害者に対して、事業主は同じことが起こらないように教育・指導を行う必要があります。
パワハラをしたことは事実としても、故意だったわけではないという管理職が圧倒的に多いことでしょう。
特に行き過ぎた指導が原因だった場合には、むしろ熱意をもって部下に接してきたからこそ起こったこととも言えます。
もちろんパワハラに当たる言動を認めないという毅然とした姿勢は重要ですが、加害者がこの事案をきっかけに変われるという気持ちを持って対応することも大切です。
加害者が研修を通して新たな気付きを得て、今後の行動に活かすことのできるようにサポートしていきましょう。
また管理職向けの研修について、内部講師による研修では後ろめたい気持ちを持ちながら受講することになるという側面があります。実施する場合にはフラットな気持ちで受講できるよう、社外の講師による研修もしくは動画による研修がおすすめです。専門講師による研修や市販教材であれば、それが一般常識であると認識させることもできます。
まとめ

ハラスメント事案が発生した時に事業主が行わなければならない対応は多岐に渡ります。大前提として被害者も加害者も大事な社員であることに変わりはありません。処分は厳正に行わなければなりませんが、両者ともに継続して社内で活躍してもらえるようにサポートすることが大切です。
特に加害者側は、よく理解出来ていない場合、同様の事案をくり返すことがあるため、節目毎の研修、毎年の研修など、組織が本気で取り組んでいることを示すことも大切です。
何よりもハラスメント事案が起きないこと、そしてもし発生しても軽微な状態で収束できることが大切です。丁寧なサポートを行いましょう。