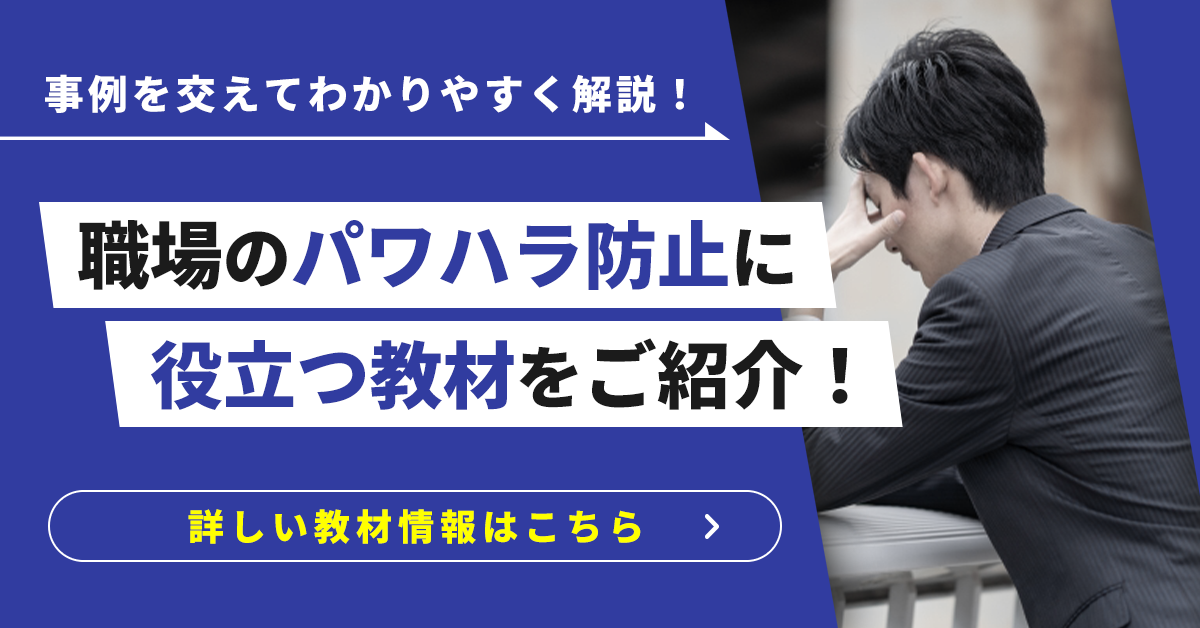ハラスメント教育には動画が最適!
この記事ではハラスメント教育の目的や手法について解説しています。
ハラスメント教育を行うのであれば動画の活用がおすすめです。この記事ではハラスメント教育の目的や動画がおすすめの理由について解説しているので、研修導入を検討するための参考にしてください。
ハラスメント教育には動画が最適!
効果的な理由もご紹介

近年職場を取り巻く問題としてハラスメントが注目を集めるようになり、どの組織でもハラスメント対策の教育に力を入れる傾向が強まっています。
ハラスメント対策の手段として研修を導入している組織が多くありますが、どのような手法を用いているかは組織によって様々です。ハラスメント教育を効果的に行うのであれば、動画による研修が最もおすすめ。
本記事では、ハラスメント教育そのものについての解説や動画による研修がおすすめの理由を紹介していきます。
職場のハラスメントとは

最近ではニュースなどでも取り上げられる機会が多くあり、ハラスメントは社会問題として世間に認識されるようになりました。
特に職場においては、部下との関わりの中でパワハラにならないようにと必要以上に意識している管理職も増えているのではないでしょうか。
「ハラスメント」とは、「嫌がらせ」や「悩ませること」を意味し、日本ではセクシュアルハラスメントの概念と共に知られることとなりました。
今ではハラスメントの認識が広まり、パワハラやセクハラといった聞きなれたものだけではなく、モラハラ、パタハラ、スメハラ、アルハラ、アカハラなどもよく知られているものです。
これらのハラスメントは働くこと自体に関わるものから、被害を受けることで心身の不調を引き起こすケースなどもあり、従業員の日常生活に支障が出る恐れがあります。
またパワハラ対策が上手くいかないと、管理職が適切な部下指導を行わず、人材育成に支障をきたす可能性もあります。企業にとっては社員の休職や退職にも繋がりやすく、深刻な社会問題として注目されているものです。
なぜハラスメント教育が企業で導入されているのか

ハラスメント教育が各企業で次々と導入されるようになったのには、社会的な背景が関係しています。
まず最初は1999年にセクハラが男女雇用機会均等法に規程され、女性労働者に対しての事業主の配慮義務が法制化されました。その後マタハラが2017年に育児介護休業法等にて法制化され、2020年にはパワハラが労働施策総合推進法(パワハラ防止法)において法制化されました。この法改正により、2020年から大企業はパワハラ防止措置を講じることが義務付けられ、2022年には中小企業にまで広げられ、国内の全ての企業にパワハラ対策が事業主に義務付けられました。
措置義務の内容についてパワハラを例に見ていきましょう。
事業主が義務付けられた防止措置は、次の3つがあります。1事業主の方針等の明確化および周知・啓発、2相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備、3職場におけるパワハラに関する事後の迅速かつ適切な対応、の3つです。併せてプライバシーの保護、相談した者に対して不利益を与えないことの周知・啓発があります。
この中の「事業主の方針等の明確化および周知・啓発」としてハラスメント教育が行われています。
尚この対策は、セクハラ、マタハラについても同様です。
ハラスメント教育を行う目的

社内でハラスメント教育を行うことで、大きく分けて3つの目的を果たすことが期待できます。ここからはそれぞれの目的について詳しく解説していきます。
社内全体でハラスメントの認識を統一する
「ハラスメント」という言葉は誰もが聞いたことあるほどに広く知られていますが、何がハラスメントにあたり、何がハラスメントにあたらないのかはとても分かりにくく、人によって認識が異なるため、必要以上に警戒して距離を取ってしまったり、過敏に反応してしまうケースが生じている職場も少なくありません。
社内全体でハラスメントの定義や事例を学ぶことで、認識を統一することができれば、このような状態を解消することが期待できます。
加害側にならないための線引きが明確になることで、意図していないハラスメントを減らすことに繋がり、安心して同僚や上司、部下とのコミュニケーションを取りやすくなるでしょう。
ハラスメントが起こりにくい職場環境をつくる
ハラスメントの起きやすさは職場風土に起因することが知られています。
ハラスメント防止を目指すのであれば、そもそもハラスメントが起こりにくいような職場環境を築いていくことが大切です。
上司の指導内容が理不尽である場合、そのことを率直に伝えられる職場であればパワハラは起こりにくいでしょう。
職場でのコミュニケーションに性的な内容があった時、すぐに相談できる状態であれば、深刻な事態に至らずに済むかもしれません。
職場の人間関係が、どのような状態であればハラスメントが起こりにくいのかを研修などで学んでいくことで、働きやすく成果の上がる職場環境づくりにつながることでしょう。
ハラスメントの被害を最小限にする
ハラスメント教育を通して、職場でハラスメントの被害に遭ったりハラスメントと思われる言動を見聞きした時の対応方法について周知していきましょう。
被害を受けるなどしたときに「ハラスメントかな?」と気づいて、社内のハラスメント相談室などに相談することができれば、深刻な被害にならずに解決出来る場合もありますし、その後の更なる被害を防ぐことができます。そのためにも、どのような言動がパワハラ、セクハラ、マタハラに相当するのかを、全社員が理解しておくことが重要です。
万が一被害に遭ったときに正しい対応方法を知っておくことは、社員自身が自分を守ることに繋がりますのでぜひとも伝えておきたいポイントです。
またハラスメントの被害者はメンタルヘルス不調に至ることも多いため、被害そのものを減らすことが出来れば、そうした心身の健康被害を減らすことにつながります。
ハラスメント教育の実施方法

ハラスメント教育をいざ行う際に対象となる範囲や研修の実施方法を決めていかなければなりません。対象となる社員や一般的に行われている研修手法について解説していきます。研修立案の参考にしてみてください。
ハラスメント教育の対象者
ハラスメント教育を誰に実施するべきかで迷う方もいるかと思います。
研修として実施するのであれば新人研修やマネジメント研修に組み込むなど、様々な選択肢があることと思います。
結論としてはハラスメント教育を行う対象者は、階層別に、上位から進めるのが効果的です。そして社員全員への研修をくり返し実施するのが望ましいと言えるでしょう。
ハラスメントをしてしまう行為者(加害者)は。より力を持つ人であることが多いためです。そのためにはマネジメント研修、新任管理職研修など、管理職向けの研修は必須です。その上で、或いは並行して、一般職向けも実施していくと良いでしょう。
対象範囲が広がれば広がるほど、時間の調整や準備など担当者としては難易度が高く感じてしまうかもしれません。
しかし、例えばパワハラ研修が不十分な場合、指導の場でパワハラが起きたり、パワハラと言われるのを避けるために指導が不十分になったりという問題が起きる可能性があります。そのため、階層別に全社員に対して実施するのがおすすめです。
一方で、全社員への実施となると研修実施者の負担が増えることにもなりかねません。負担を減らしながら行うためにも効率的に実施する工夫が必要です。
ハラスメント教育の研修手法
ハラスメント教育の研修を行う手法には主に「対面での研修」「オンラインでの研修」「動画での研修」の3種類があります。
対面での研修であれば、講義に加えてロールプレイングを伴うことが可能です。
複数の店舗を抱えていたり、支社が全国にあるなど社員を 一堂に会するのが難しい場合には、オンラインでの研修を行うことで効率的に実施することができます。
また、動画による研修も研修運営側、受講側それぞれにメリットが多くあるため近年導入する企業が増えている手法です。
研修手法については明確な定めはありません。そのため、人事担当者や研修担当者が自社の状況や課題に合わせて有効な方法を検討して選択することになります。
ハラスメント教育に動画がおすすめの理由

ハラスメントについての知識をただ知っているだけでは、せっかく行ったハラスメント教育も効果が半減してしまいます。当事者意識をもって研修直後から行動の変化が期待できるよう、効果の出る研修を行いたいところです。
効果的な研修実施という側面においても動画を活用するのはおすすめです。その理由を解説していきます。
リアルなイメージを持たせやすい
研修動画であればコンテンツとして映像を差し込むことが可能です。事例ドラマを取り入れることで、リアルなハラスメントの情景を受講者に届けて具体的なイメージを持ってもらうことができるようになります。
ハラスメントの態様を抽象的な言葉で理解するよりも、どんな場面なのか、或いはどんな言い方・表情が問題になるのか、などを理解しやすくなります。
資料等による講義形式よりも印象的になり、映像のインパクトから研修受講後も受講者の記憶に残りやすくなるでしょう。
短時間でも効果を得やすい
>動画のコンテンツは、事例と解説だけの短い物もありますし、市販のコンテンツでも20~30分程度のものが販売されています。同様の内容を講師による研修で計画すると、90分や120分になることも少なくありません。
動画コンテンツを配布資料と組み合わせたり、eラーニングとして使用したり、様々な隙間時間の活用で効果を上げることも可能です。
まずは知識として知っておくということは大切なことですし、再度見返すことができるのが動画研修の活用しやすいところです。ハラスメント防止の効果にも期待できるでしょう。
まとめ

職場でハラスメント事案が発生してしまうと、企業は大きなダメージを受けることになります。活躍している社員の休退職を招くことで人材不足を引き起こすだけでなく、社会から見た企業のイメージも損ないかねません。
効果的なハラスメント教育を行うことで、社員が心身共に健康に働くことのできる職場環境を目指すことができます。動画によるハラスメント教育を取り入れて、より安心・安全な職場づくりを進めてみてはいかがでしょうか。