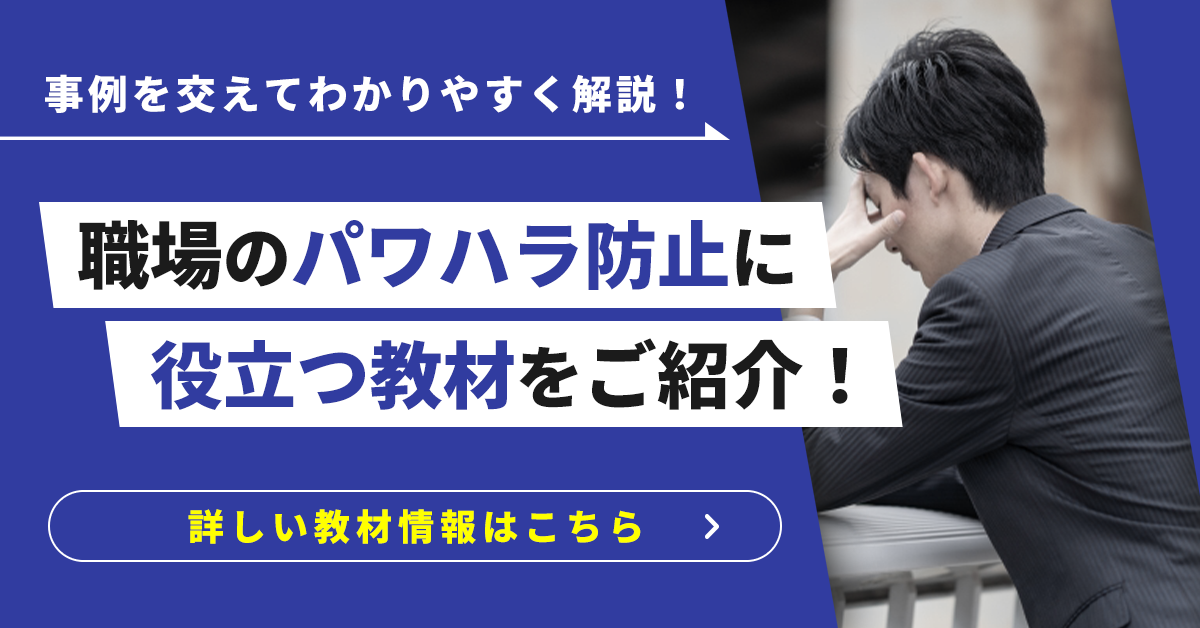パワハラ研修はなぜ必要?
近年、パワハラに関する研修を導入している企業は増加傾向にあります。
社内で研修の立案や実施のために頭を悩ませている人事担当者の方も多いのではないでしょうか。
この記事ではパワハラ研修が必要とされている背景や、パワハラ防止策として効果的な研修コンテンツについて解説しています。
ぜひ研修を導入する際の参考にしてみてください。
パワハラ研修はなぜ必要?
研修の目的や内容についても紹介

パワハラが注目を浴びるようになってから、パワハラを未然に防ぐために各企業では積極的にパワハラ研修が行われています。
社内で研修の運営を担当されている方の中には、パワハラ防止に繋がるより効果的な研修を行うための方法を検討されているという方もいることでしょう。
パワハラは被害者はもちろん加害者にも大きなダメージを与えることになります。
社内で起こった場合には会社もダメージを受ける可能性があるため、企業としてもパワハラが発生しないように環境を整えていくことが必要です。
この記事では企業がパワハラ研修を行う理由や、その内容について解説しています。
ぜひ社内でのパワハラ研修を検討されている方は参考にしてみてください。
パワハラの定義とは
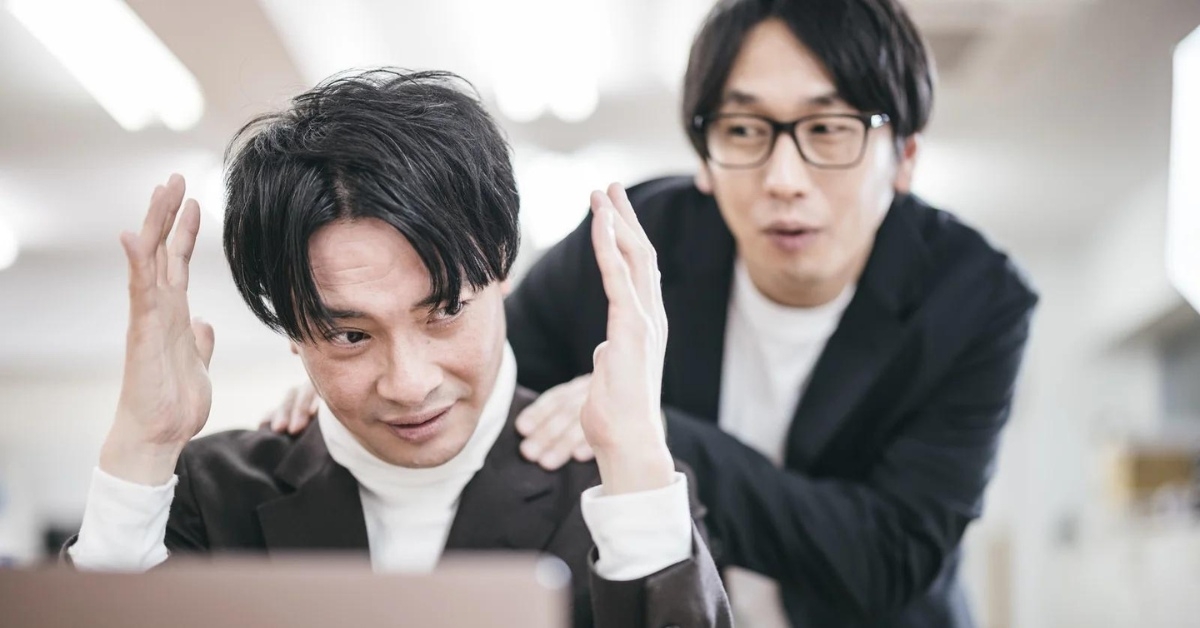
パワハラという言葉を聞いたことがないという人はほとんどいないと言えるほど、頻繁に耳にするようになりました。
しかしパワハラと指導の線引きをするのは難しく、些細なことでも「これはパワハラではないか」と必要以上に気にしてしまう場面も多いのではないでしょうか。
厚生労働省は、パワハラは以下の3つの要素を全て満たす言動であると定義づけています。
【パワハラの定義】
次の3つの要素を全て満たす言動が、職場の「パワーハラスメント」と定義されます
- 優越的な関係を利用した言動
- 業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動
- 就業環境を害する言動
それぞれの要素について詳しく解説していきます。
優越的な関係を利用した言動
上司と部下という関係において、上司は優越的な立場にあるということができます。
このように上司からの叱責などは、パワハラになりやすく注意が必要です。
また、パワハラというと一般的には役職の高い人から低い人への言動と考えられがちですが、実は業務上で必要とされる知識や経験の量も優越的も「優越的」に該当する場合があります。そのため、同僚や部下であっても、加害者側になる可能性があるので注意が必要です。
業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動
社会通念上、業務の目的から大きくそれた言動や不要と思われる言動が該当します。
厚生労働省は、次の6つの類型を示しています。
- 身体的な攻撃:暴行・傷害
- 精神的な攻撃:脅迫・名誉毀損・侮辱・ひどい暴言
- 人間関係からの切り離し:隔離・仲間外し・無視
- 過大な要求:業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害
- 過小な要求:業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと
- 個の侵害:私的なことに過度に立ち入ること
例えば、部下に指導する際、大勢の前で強く叱責するのは、精神的な攻撃に相当する可能性があります。見せしめと捉えられる可能性があり、例え指導内容が適切であったとしても、大勢の前で強く叱責することが侮辱と考えられるためです。
このように行き過ぎた言動は「業務上必要かつ相当な範囲」を超えてしまう可能性があります。
しかし、強めの言葉で指導したとしても、「業務上必要かつ相当な範囲」を超えるとは言えない場合はパワハラには該当しません。同じような言動であっても、そのプロセスや人間関係によって異なるので、注意が必要です。
就業環境を害する言動
分かりやすいのは、精神的または身体的な苦痛を与えて就業環境を害する事例です。
例えば、ある社員が上司や先輩の言動が原因で体調を崩したり、仕事への支障が出たというように、「就業する上で看過できない程度の支障が生じること」を指します。
この場合の「就業環境が不快」と感じる程度は「平均的な労働者の感じ方」で判断されます。その際「社会一般の労働者が、就業する上で看過できない程度 の支障が生じたと感じるような言動であるかどうか」が基準となります。
パワハラ研修が企業にとって必要なのはなぜか

2020年の厚生労働省の調査によると、過去3年間にパワハラを受けたことのある人の割合は約31%に達しており、様々な公的機関への相談も増加しています。誰もがパワハラという言葉を知っているだけでなく、少なくない労働者が被害を受けている実態があります。
パワハラが社会問題としても認識されているという背景もありますが、なぜ各企業はこれほどまでにパワハラ研修の実施をする必要があると考えているのでしょうか。
その主な理由には以下の3つが考えられます。
- 適切な指導を行い人材を育成するため
- パワハラによるメンタル不調などによる労働の損失を出さないため
- 被害者、加害者それぞれからの訴訟リスクに備えるため
適切な指導を行い人材を育成するため
パワハラという言葉は当たり前に使われるようになりましたが、その理解度は社員によってまちまちなのが実情です。
パワハラ当事者になることを必要以上に恐れてしまい、部下の育成に支障が出ているという上司を抱える企業も多いことでしょう。しかし部下指導に及び腰になると、人材を育成することに支障が出てしまいます。
このような状況を避けるためにも、社員全体が同程度の知識を共有していることが大切です。
研修を実施することで認識を統一できるので、上司・部下ともに安心してコミュニケーションを取りやすくなるでしょう。
パワハラによるメンタル不調などによる労働の損失を出さないため
パワハラが起こってしまうと、被害者は心身の健康を害することが多くなります。
幾らメンタルヘルス対策を行っても、その傍らでパワハラの被害が起きてしまうのでは意味がありません。
メンタルヘルスに支障が出れば、被害者の業績は悪化しますし、そうした労働者を抱える部署全体の生産性も落ちてしまいます。
またそのような雰囲気の悪い職場からは人材も流出していくため、誰もが安心して働ける環境を保持することが重要なのです。
優秀な人材の流出を防ぐためにも、パワハラが起こらない職場環境を整えることは重要です。
被害者、加害者それぞれからの訴訟リスクに備えるため
増加傾向にあるパワハラを防ぐため、2020年6月にパワハラ防止法が施行されました。
大企業はこの法律によりパワハラ防止策を講じることが義務付けられ、その手段として研修の導入が加速していきました。
さらに2022年の4月には法改正が行われ、対象が大企業のみから中小企業まで広がることとなりました。
この法改正を受け、国内の全企業がパワハラ防止措置を取ることが義務付けられたため、その措置の一つとしてパワハラ研修の導入はますます加速しています。
対策が不十分な場合、もしパワハラの訴えが起きた場合、被害者側からは適切な対策をとらなかったことを訴えられることがあり、きちんとした処分が出来ない場合は加害者側から訴えられることもあるなど、訴訟リスクへの対策という観点からの対応が不可欠です。
パワハラ研修の内容

パワハラ研修の具体的な手法や構成、コンテンツは企業によって様々です。
社内で一から考えて研修を作成しているという企業もあれば、外部委託している企業もあります。
ここでは効果的なパワハラ研修にするために、取り入れるべき内容として以下の3つをご紹介します。
- パワハラとはどのようなことか(定義、類型など)
- パワハラの事例
- パワハラと指導の違い、判断のポイント
それぞれの内容について詳しく解説していきます。
パワハラとはどのようなことか(定義、判断基準)
「パワハラ」の言葉は知っていても、社内の認識はかなりばらついていることがあります。そのため、パワハラとはどのような言動のことを指すのかという定義について、全体の認識を統一させておくことが大切です。
全体の認識を揃えることができれば、上司は必要以上に過敏になることなく、部下指導を行ったり、コミュニケーションを取ることができるようになります。
部下の側も、何でも「パワハラ」というようなことがなくなり、厳しい指導を「指導」として受け止めることができるようになります。
その結果、社員同士の連携を活性化させることにも繋がり、安心できる職場環境をつくることもでき、業務の生産性向上が期待できます。
研修の機会に「パワハラとはどのようなことか」を明確にしておくようにしましょう。
パワハラの事例
パワハラは指導などに関わるコミュニケーションの中で生じるため、誰もが当事者になる可能性があります。
定義だけではピンと来なくても、具体的な事例を共有することで、どんな言動がなぜパワハラとなるのかが理解しやすくなります。
社内事例や同業種の事例を共有したり、動画の事例ドラマを活用するなど、リアルに伝えることで、より身近に感じることができます。
研修コンテンツの中には積極的に事例共有を取り入れるのがおすすめです。
パワハラと指導の違い、判断のポイント
パワハラ研修で重要なことは、「パワハラ」と「指導」の違いをきちんと理解することです。
パワハラが起きるとするとその多くは部下指導の場であるため、上司の側はパワハラにならない指導のポイントをきちんと理解しておくことが不可欠ですし、部下が指導とパワハラの違いを理解していない場合、「自分が不快に感じる指導」を全部「パワハラ」だと思い込んでしまう可能性もあるのです。
適切に部下指導が行われるためには、上司も部下も、両方がパワハラになる時、パワハラにならない時を理解しなければなりません。
またパワハラ行為者になる人は、「自分だけは大丈夫」と思い込んでいる人が少なくありません。そのため研修では、誰もが加害者になる可能性があることを伝え、チェックリストなどで普段の自分の言動を振り返ることができるようにすることがおすすめです。
まとめ

パワハラ事案はどの企業でも起こる可能性があります。
パワハラ事案が発生することで当事者だけではなく、周りの社員や企業イメージにも影響が出るため、出来る限りの策を講じて発生を防ぎたいものです。
社員が安心して働くことができる環境を整えるためにも、パワハラ防止のための研修を積極的に取り入れてみましょう。
より効果的な研修内容にするためには、自社で完結させて行うよりも外部委託する方がおすすめです。
高い効果を期待できるので、検討してみてはいかがでしょうか。