研修動画の制作手順を徹底解説!
社内研修を充実させるにあたり、研修動画制作に取り組む企業が増えてきています。研修動画を活用することで、これまで以上に効率的且つ効果的に研修を実施することが可能です。本記事では、研修を動画で行うメリットや制作する上でのポイントを徹底解説します。ぜひ研修動画制作の参考にしてみてください。
研修動画の制作手順を徹底解説!
効果的に活用するためのコツも紹介

ハラスメント研修、新入社員研修、コンプライアンス研修、マネジメント研修などの豊富な研修制度を設けている企業が多くあります。社内の人財が育成されていく一方で、その分研修の企画や運営に多くの時間を費やしている人事担当者の方も多いのではないでしょうか。
近年では、豊富な研修制度を効率よく運用していくために研修動画を活用する企業が増えています。
本記事では、研修動画の導入を検討している人事担当者の方に向けて、研修動画の制作手順やその際のコツをご紹介します。ぜひ参考にしてみてください。
研修動画とは

研修手法は様々ありますが、動画研修を導入する企業が増えています。繰り返し活用できることからコストパフォーマンスが良い、受講者個々のスケジュールに合わせて実施できることから業務との両立がしやすいといったメリットがあるためです。
研修動画を制作するにあたって、企業に依頼するという方法もありますが、自社制作をする企業も増えています。
外部企業に依頼すればコストはかかりますが、クオリティの高いものを作成できます。人事担当社員の負担は大幅に軽減できるのもメリットです。
自社制作であればコストを抑えられ、且つ自社ならではの内容を盛り込みやすいというメリットがあります。しかしながら、担当者の負担は大きくなり、制作までの時間がかかることが予想されるので業務整理が必要になるでしょう。
研修動画を制作すること自体はメリットが多くありますが、目的や求めるクオリティ、社内状況に応じて制作方法は使い分けるのがおすすめです。
研修動画を制作するメリット
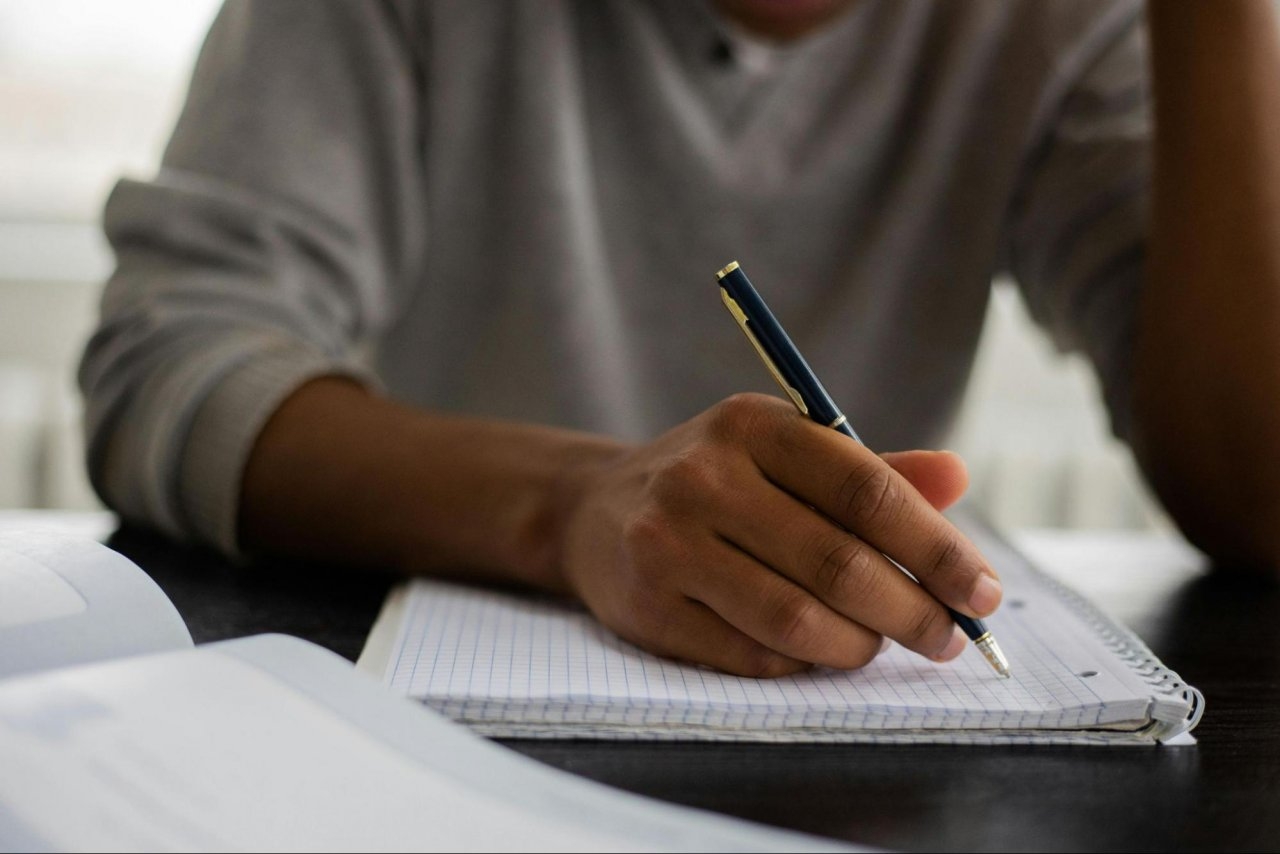
これまで研修というと対面で実施する方法が主流でしたが、近年では動画による研修を実施する企業が増えてきています。在宅勤務やリモートワークといった新たな勤務形態が増えた背景もあり、これまで以上に需要が高まり注目された研修方法です。
アフターコロナの現在でも、研修動画は各企業で継続的に活用されている傾向にあります。動画研修を導入している企業が考える研修を動画化するメリットを2つご紹介します。
各自が最適なペースで受講できる
動画研修は一斉に研修するのはもちろん、従業員自身が必要を感じた時に都度振り返り学ぶことが可能。明確に研修受講の機会を設定するのも大切ですが、最も集中して自主的に学ぶのは受講者本人が必要性を感じた時です。例えばシステムの操作方法を伝える研修であれば、実際に使用する時の受講が最も効果的。しかし、必要に感じるタイミングは人それぞれ異なります。
動画研修であれば、それぞれのタイミングで受講できるので必要な情報を確実に学んでもらうことが可能です。さらに自分の理解度に合わせて動画を止めてメモを取ったり、繰り返し視聴することができるので、それぞれのペースに合わせた高い習熟度を期待できると言えるでしょう。
業務への支障を最小限に抑えられる
どのような企業でも従業員それぞれで担っている業務は異なり、各部門の繁忙期も様々です。従業員全体に向けた研修を一斉に行おうとすれば、決まった日程のまとまった時間を研修に充てることになります。本来の自分の仕事を研修のために調整する必要が出てくるので、モチベーションの低い状態で受講する人も出てきます。
動画研修であれば、受講者が自分の業務スケジュールの中に研修の時間を設けて受講することが可能になります。落ち着いて受講でき、モチベーションも保ちやすい環境を整えられるため、前向きに受講してもらいやすくなるのは大きなメリットです。
研修効果としても好影響であると言えるでしょう。
研修効果を高めることに期待できる
他の研修手法と明らかに違うポイントは、研修動画であれば必要に応じて様々な映像を差し込むことができるということです。
例えば、マニュアルを伝えるような研修を作成する場合、ただスライドや解説を加えるだけでは具体的なイメージが難しい可能性があります。
しかし、研修動画であればマニュアルを活用する手順を事例ドラマ化して具体的なイメージを促すことが可能です。動画を視聴することで印象的になるため、実際の場面で身につけた知識を活用しやすくなります。
研修動画の種類

研修動画には大きく分けて以下の4つの形式があります。
- マニュアル型
- セミナー型
- ドキュメンタリー型
- 事例ドラマ型
いずれも企業で制作されている研修動画の主流の形式ですが、効果的な研修動画に仕上げるためには適切な形式での研修動画を制作することが大切です。
実施する研修の目的に合う特長を持っている形式を選択して制作に移りましょう。
ここからは、それぞれの概要・特長についてご紹介していきます。
マニュアル型
システムの操作の仕方や接客の仕方などの自社で活用しているマニュアルを伝えるのが「マニュアル型」の研修動画です。
社内で決まっていることを、誤りなく確実に伝えることが求められる研修に適しています。
マニュアル化しているものを動画で伝えることで、全社員に同じ内容を同じクオリティで教えらえる点が最大のメリットです。
さらに口頭では説明しづらいことも、動画や画像を組み入れた研修動画にすることで、わかりやすく説明することが可能になります。
研修動画を視聴する際に、確認できる資料などを別途配布しておくとさらに効果的です。
セミナー型
対面で行う研修を撮影し、動画化したものが「セミナー型」の研修動画です。
セミナー型は話者の熱量が伝わりやすいのが特長。社長や経営陣からのトップメッセージなどの社員に想いを伝える内容の研修に最適です。
また、実際に行われている研修をそのまま動画化することができるので、時間や費用を抑えられるというメリットがあります。
一つのテーマを全受講者に同じ温度感で伝えることが求められる研修において有用な形式です。
ドキュメンタリー型
社員のインタビューや働いている姿を撮影したものが「ドキュメンタリー型」の動画です。
現場のリアルな雰囲気をダイレクトに伝えることができるので、会社説明会などでの活用に適しています。
やや長尺の動画になったとしても、興味をもって見ることが出来るため、受講者が飽きにくいのが特長です。リクルート用など、現場の空気感を伝えるメリットがある場合に有用な形式と言えるでしょう。
事例ドラマ型
研修で伝える内容をイメージしながら習得できるよう、再現映像などを事例ドラマとして組み入れているのが「事例ドラマ型」の研修動画です。
例えば店舗でのお客様対応やハラスメント研修などにおいて、具体的なシーンを見せることでリアルな状況をイメージすることができます。
例えばハラスメント防止研修用であれば、どんな言動が厳しいと思われるのかなどを映像として伝えることができるので、受講者の理解度が高まるのが特長です。さらに、専門家のインタビュー等の解説があれば、より深い理解に繋げることができるでしょう。
研修動画制作ステップ

研修動画を制作をする際の手順を解説していきます。
全体の流れを計画して、それぞれのステップを進めていくことでスムーズな研修動画の制作に繋がります。自社制作の場合にも外部委託の場合にも、作業工程に大きな違いはありません。
研修動画完成までのスケジュール感を掴むためにも全体像を確認しておきましょう。
1.動画研修の目的と伝えたいテーマを決める
まずは動画研修を実施する目的と対象を明確にしましょう。その研修によって、どんな効果を得たいのかを具体的にします。
目的を明確にしたら、伝えたいテーマやメッセージを言語化しましょう。
このプロセスが、その後の工程で動画研修を固めていく際の軸となります。
2.動画構成を考える
続いて、動画の構成を考えます。
伝えたいテーマが受講生に伝わりやすくするためには、どのようなステップが望ましいのかを明らかにしていきましょう。
「オープニング」「概要説明」「〇〇についての説明」といった構成を考え、動画のイメージを具体化していく作業です。
3.シナリオの作成
具体化した動画構成を基にして、映像としてどんな研修を制作するのかを具体化していきます。
動画の流れや説明のナレーションをシナリオ化していきましょう。どのような映像で何を説明するのか、どのような図・表が入るのかなどを考えながら進めていきます。シナリオはナレーションの原稿であるだけでなく、動画全体の設計図でもあるので、シナリオによって、どの場面で何が必要なのかが決まっていきます。必要に応じて絵コンテを用意する方法もあります。
4.動画素材の撮影
シナリオで明確になった実写素材の撮影を行います。
小道具の準備、資料の作成や撮影会場の確保など、下準備も忘れずに行いましょう。
また撮影を迎える前に撮影機材やマイクなど機材の確認をしたり、リハーサルを行っておくと、撮影当日をスムーズに迎えられると共に、効果的な動画制作に繋がります。
屋外での撮影を予定する場合は、天気予報の確認も忘れずに。
5.ナレーション録音
動画に挿入するナレーションの録音を行います。(編集後にナレーションの録音をする方法もあります。)
録音の精度を都度チェックしながら 進めていくのがおすすめ。
専門のレコーディングスタジオやプロへの依頼でない限り、日をまたいだり別な場所で録音すると、音の質が変わってしまう可能性が高いため注意が必要です。
後でNGが判明し、録音し直すことのないように、音量や言葉尻、イントネーションなどを確認しながら進めましょう。
6.動画編集
素材が全て揃ったら、いよいよ編集に入ります。
不要な箇所のカットや、アニメーションやテロップ、BGMなども積極的に取り入れて効果的な研修動画の完成を目指します。研修が目的の動画なので、きちんと伝えるべきことを文字化するのが効果的です。
他から動画・イラスト・写真・音楽などの素材を入手する場合は、必要な著作権をクリアしているかの確認を忘れずに。
制作した研修動画を効果的に活用するコツ

研修動画を活用するメリットは豊富にありますが、一方でデメリットと言えることもあります。デメリットは制作時の工夫次第で解消することが可能です。社内でより効果的に研修動画を活用するために、抑えておきたい制作時のコツを2点ご紹介します。
アウトプットをセットで設計する
動画研修では、受講者一人で受け身で研修を受けることが一般的です。
そのため、個々の習熟度に差が出てしまう可能性があります。
受講者全体を一定の習熟レベルに保つため、アウトプットをセットにして研修を設計するのがおすすめ。
具体的には、研修受講後に簡単なチェックテストを取り入れてみるのが効果的です。
また、研修の振り返りやブラッシュアップを進める際の参考にもなり、研修運営側にも大きなメリットがあります。
実施する際には集約する手間が省けるので、紙媒体ではなくデータでの運用がおすすめです。
まとめ

研修動画は受講者にも運営側にもメリットの多い研修方法です。動画の制作時に工夫を加えることで、質の高い研修動画を制作することができます。効果的な動画研修を導入することで、研修担当者の業務を効率化させ、より一層社員研修を充実させることも可能です。研修のデジタル化をまずは研修動画化するところから進めてみてはいかがでしょうか。

