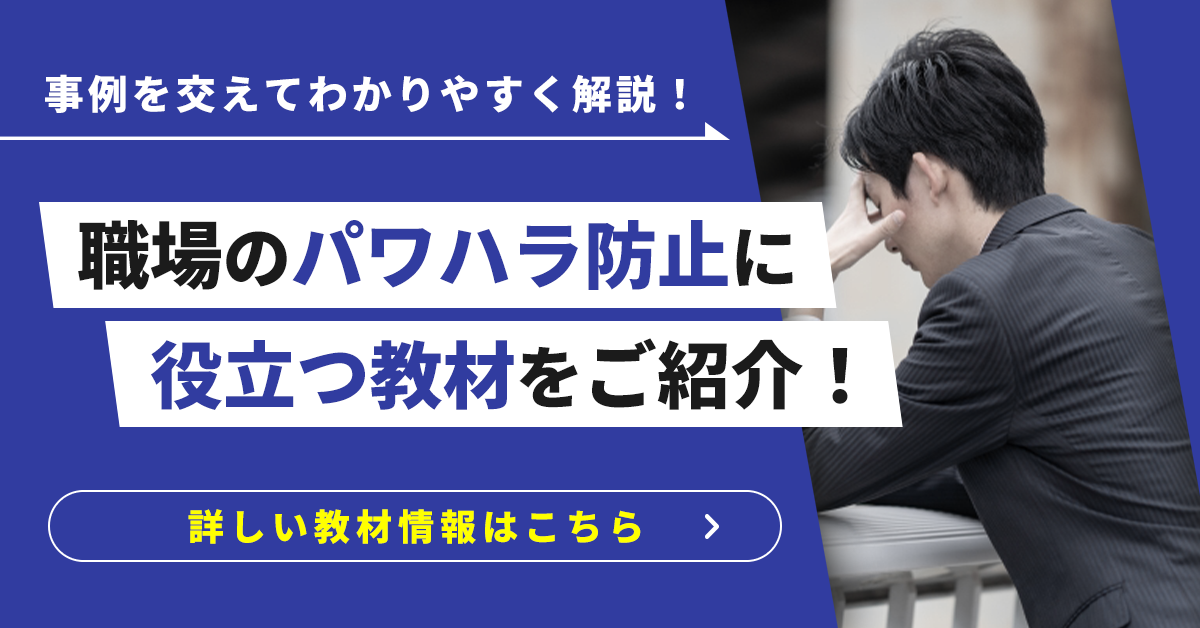ハラスメント研修はもはや必須!
近年、ハラスメントに対する世間の注目度は飛躍的に上がってきています。ハラスメントの法整備も進み、対策を強化している企業も増加傾向にあります。主な対策として講じられているのが研修の導入です。本記事では、ハラスメント研修の必要性やその内容について解説しています。ぜひ社内で実施する際の参考にしてみてください。
ハラスメント研修はもはや必須!
取り組む必要性と研修の内容を解説

近年の職場の問題として、ハラスメントという言葉を耳にすることが増えてきています。社会問題としても取り上げられ、全国的に関心の強い事柄の一つです。しかし、これだけ注目を浴びるようになっているものの、職場で取り組む必要性やその正しい理解に至っている人は多くないというのが実情です。そのような背景から、ハラスメント研修を社内で行う企業が年々増加しています。
本記事では、ハラスメント研修を行う必要性や研修の内容について解説しています。これから導入を検討されている方、見直しを検討されている方もぜひ参考にしてみてください。
ハラスメント研修が注目されている理由

ハラスメント研修が各企業で導入されるようになったのには、パワハラに関する法改正が大きく関与しています。
2020年6月に「改正労働施策総合推進法」が施行されたことにより、大企業にパワハラの防止措置を講じることが義務付けられました。また、続いて2022年には対象となる企業の範囲が中小企業にまで広がりました。これにより、現在では日本にある全ての企業に、パワハラ防止措置を講じる義務があります。
このパワハラ防止措置とは、事業主に対してパワハラ防止の「方針等の明確化および周知・啓発」、パワハラ等の「相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備」、「職場におけるパワハラに関する事後の迅速かつ適切な対応」の3つからなり、事業主の「方針等の明確化および周知・啓発」の手段として各企業ではパワハラ研修が積極的に導入されています。
このような背景から、ハラスメント研修はこれまでハラスメントに関する注意喚起をしていなかった企業からも注目されている研修となっています。
職場でハラスメント研修を実施する目的

職場のハラスメント研修は、ハラスメントの無い職場をめざすことが目的です。
「ハラスメント」という言葉を知らないという人はほぼいないという程に、ハラスメントは浸透してきています。しかし、定義を理解しているというほどではない人が多いというのが実情です。
上司が部下に対して指導したりコミュニケーションを取る際に「パワハラやセクハラにならないように気をつけないと…」と必要以上に警戒して、指導を避けがちになるということも少なくありません。
また、ハラスメントは誰もが加害側にも被害側にもなる可能性があります。多くのハラスメントは上司から部下への加害ですが、上司が部下からハラスメントを受ける可能性があるということを知らない人はまだ大勢いることでしょう。
適切な指導を行い、健全なコミュニケーションが取れる環境を整えるためにも、そもそもハラスメントとは何なのか、どのような行動がハラスメントにあたるのかを社歴や役職に関係なく、すべての働く人が正しく理解することが必要です。
ハラスメントの種類と特徴

職場のハラスメントにはたくさん種類があると言われることがあります。しかし防止することが義務化されているのは、防止対策が法制化された3つのハラスメント、つまりパワハラ、セクハラ、そしてマタハラの3つです。具体的にはどのような内容なのか確認しておきましょう。
パワハラ(パワーハラスメント)
パワハラとは、上司と部下・先輩と後輩・ベテランと新人といった力関係のある間柄で、その力(パワー)を背景にした言動をいい、最も相談件数の多い職場のハラスメントです。
具体的には、以下の3つの要件がすべて満たされた場合パワハラであると定義づけられています。
- 優越的な関係を背景に行われる言動
- 業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの
- 労働者の就業環境が害されること
上司からの暴力や暴言、こなせるはずのない量の仕事の押し付けなどであればパワハラであろうとの判断がつきやすいのですが、パワハラの難しいところは、熱心な上司・先輩が相手のために良かれと思ってする指導がパワハラであったり、受け手側が「叱咤激励」を「パワハラ」として捉えることも少なくないという点です。とはいえ、上記の3点を全て満たさなければパワハラには該当しないため、相手が不快だと受け留めただけではパワハラにはなりません。
更に「パワハラ」と言われることを避けるために指導に及び腰になる上司も少なくないこと、上司の指導の理不尽さからメンタル不調や離職に至るケースも多いのが実情です。
相互に「パワハラとは何か」を正しく認識しておくことで、このような混乱と人財の喪失を防ぐことができます。
セクハラ(セクシュアルハラスメント)
セクハラとは、働く人が、職場における性的な発言や行動による嫌がらせなどにより、労働条件の不利益を被ったり、就業環境が害されることを指します。
労働条件について不利益を被る例(対価型)としては、性的な言動を拒否したら解雇されるなどがあります。また就業環境を害される例(環境型)としては、性的な事実関係に関することを話題にしたり、不快に感じる性的な発言などの結果、仕事に集中できなくなるなどの影響が出ることが該当します。
セクハラで勘違いが起きる場面として、激励や鼓舞の意味合いで肩をポンと叩いたり、体力面を気にかけて「力仕事は男の仕事だから」という言葉かけなどがありますが、こうした例もNGとなる可能性があります。例え行為者に配慮や気遣いのつもりがあったとしても、相手が不快に感じる場合はセクハラとされる場合があるので、特に上位のポジションを持つ人が取るコミュニケーションには注意が必要です。
さらに、セクハラは男性から女性に対して気を付けるものという印象が強いですが、性別は関係ありません。女性から男性に対して、同性同士であっても該当することがあるので社員全員への注意喚起が必要となるのがポイントです。そしてLGBTQについての正しい知識を持つことも求められています。
マタハラ(マタニティハラスメント)
マタハラとは、妊娠・出産・育児休業などを理由とする「不利益な取り扱い」と「嫌がらせ」のことを言います。更に上司や同僚からのマタハラとして、「状態への嫌がらせ型」と「制度等の利用への嫌がらせ型」があり、育児休業については男性労働者も対象となります。
「不利益な取り扱い」の例として、上司が妊娠の報告を受けた時に、「ちょうど産休に入るのは繁忙期になるのか。それじゃあ戻る席はないよ。」といった妊娠したら解雇や雇止めを示唆する発言をしてしまうほか、降格や減給などがあります。
上司や同僚からの「状態への嫌がらせ」の例として、つわりに苦しむ女性にたいして「つわりは病気じゃないから気にし過ぎない方が良いよ。」などの発言や、「制度等の利用への嫌がらせ」の例として、妊婦健診のための休暇申請に対して、「忙しいのによく休暇の申請ができるな」などの発言などがあります。
他にも、妊娠した女性本人に確認せずに「今は体調優先だから、この仕事は違う人に任せるね。」などと仕事内容の一方的に変更をすることもマタハラになる可能性があるのが難しいところです。例え部下のことを思っての言動であっても、体調も仕事への思いも人によって異なることから、一方的に進めていくのは避けましょう。男性労働者の育休取得についてのハラスメント(パタニティハラスメント)も問題となるなか、当事者と上司の双方で話し合いながら進めていくことが重要です。
ハラスメント研修の計画

ハラスメント研修を実施する上で取り入れておくべき内容について紹介します。効果的な研修を実施するためには、階層ごとにポイントを絞って実施すること、毎年実施するなど継続して行うことが大切です。研修立案の参考にしてみてください。
ハラスメントへの理解促進
それぞれのハラスメントの定義と判断のポイントをきちんと理解すること、社内で生じる可能性が高いものや認識にばらつきや誤りのある事を中心にし、自分が行為者にならないのはもちろんのこと、もし被害を受けた時には相談などの解決に動けるように、会社や周囲の制度を理解することが大切です。特に管理職は、部下からの相談に対してもきちんと対応できるように、より正しく理解・対応することが求められています。
また管理職に向けた内容が必要であると同時に、一般職に対しても、何がどんなハラスメントに相当するのかを知らせることが大切です。そして一般職であってもハラスメントの行為者になる場合があるため、自分が加害をしないための知識も必要です。
ハラスメントの判例・事例共有
実際にハラスメント事案が争点となった判例や、実際の事例を共有するのがおすすめです。どのようなことが起こっているのか、どんな損害が当事者や会社に生じるかをリアルに伝えることで、危機感を持ってもらいやすくなります。可能であれば自社内の事例の詳細を加工して開示したり、同業他社の事例を共有できるとより身近に感じることができるでしょう。「明日は我が身」と思ってもらえるような工夫が必要です。
アウトプットの機会を用意
一方的に情報を受け取っているだけでは「理解したつもり」になりがちです。ハラスメント研修を受けた後、ハラスメント防止に向けた行動変容に繋げることが大切です。そのためにも、グループディスカッションを行ったり、チェックリストによる自分自身のチェックを研修の中に組み入れるなど、アウトプットの機会を用意するのがおすすめです。自分の行動を振り返りながら取り組むことで、行動や意識の変化を期待できます。
まとめ

全ての企業にハラスメント防止措置が義務付けられているため、ハラスメント研修は必須と言ってよいものです。ハラスメント研修を適切に実施することによってハラスメントに関する正しい知識を社員が持つこととなります。そして人間関係のストレスが減り、従業員のメンタルヘルスを健全に保つことにもつながります。適切な指導も進むことから業績アップにもつながることでしょう。心理的安全性を高めて働くことのできる環境を整えるためにも、効果的なハラスメント研修の導入を検討してみてはいかがでしょうか。