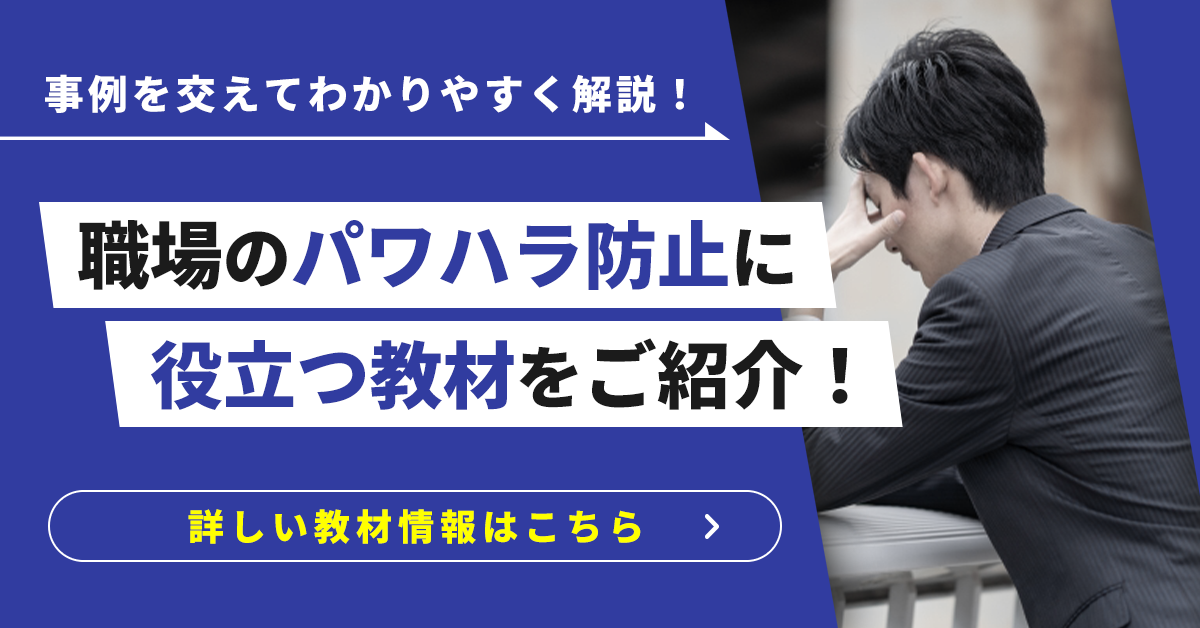パワハラ研修なら動画がおすすめ!
社会問題にもなっているハラスメントの対策として研修を実施している企業が増えています。中でもパワハラ対策は喫緊の課題として、関心が高まっています。研修の方法は様々ありますが、効果的で負担が少ない動画研修による実施がおすすめ。本記事ではパワハラ研修の目的や内容、動画研修の特長について解説します。
パワハラ研修なら動画がおすすめ!
実施の必要性・メリット・デメリットを解説

パワハラ防止対策を進めることは単に職場を社員にとって働きやすい環境にするだけでなく、業績アップや社員のウェルビーにもつながるなど、企業として講じる必要のあるものです。時代背景もあり、社内で研修を実施している企業が増えてきていますが、その中でも多いのが動画による研修実施です。この記事ではパワハラ対策の必要性や動画研修が選ばれる理由についてご紹介していきます。
パワハラ研修はなぜ必要なのか?

ここ数年でパワハラ研修という言葉を耳にする機会が増えてきました。人事担当者の方の中にはパワハラ研修の実施を求められている方も多くいることでしょう。しかし、そもそもなぜパワハラ研修を導入している企業が増えているのでしょうか。
ハラスメント対策が注目されるようになった世の中の動きや実態をご紹介します。
パワーハラスメント対策が法制化
2020年6月に「パワハラ防止法」が法制化され、まず大企業に対して、さらに2022年4月からは中小企業に対しても義務化されました。 パワハラ防止措置として定められている内容は大きく分けて「事業主の方針等の明確化および周知・啓発」「相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備」「職場におけるパワハラに関する事後の迅速かつ適切な対応」の3点があります。 この「事業主の方針等の明確化および周知・啓発」のために有効な手段となるのがパワハラ研修です。パワハラとなるのかどのようなことかを明確にして、就業規則などの社内のルールを整備し、全ての従業員に周知・啓発することが求められています。
パワハラの発生状況
厚生労働省の総合労働相談の施行状況によると、労働者から毎年100万件を超えた相談が寄せられており、中でも、パワハラ等につながる「いじめ・嫌がらせ」の相談は7万件近く寄せられています。パワハラ対策が法制化されて、様々な施策を講じている企業は増えてきていますが、未だ現場では多くの問題が生じ、うつ病などのメンタルヘルス不調や、従業員の離職につながるケースも少なくありません。 従業員が安心安全に働ける職場環境を保持することは、企業のリスクヘッジに留まらず、メンタルヘルス対策や離職防止、業績の向上にもつながるため、企業にはこれまで以上に防止対策が求められてきています。
パワハラ研修の実施で得られる効果

パワハラ研修を企業内で実施することで、具体的にはどのような効果が得られるのでしょうか。企業にとっての大きなメリットを2つご紹介します。
時代に合った企業風土の醸成
パワハラは社会問題として捉えられています。その課題に懸命に取り組み、パワハラを抑制する風土のある企業になれば企業イメージは間違いなく上がるでしょう。
また、社員採用の面においても好影響が見込めます。就職活動や転職活動をする求職者にとって、仕事内容はもちろんですがこのような時代だからこそ職場環境が大変重視されています。パワハラ対策に妥協しない風土があれば、応募者の増加にも繋がり安定した雇用を生み出すことができるでしょう。
さらに、精神的な安定が保たれることでメンタル不調者を減らすことにも期待できます。メンタル不調が原因の休退職を減らすことで、社内全体のモチベーションの維持にも繋がるでしょう。
優秀な人材が増える
パワハラ研修を実施することでパワハラに対する共通認識を上司・部下それぞれで持つことができます。
パワハラに対して過敏に意識してしまうあまり、部下とのコミュニケーションが円滑に取れずに適切な指導ができないという悩みを抱える上司は少なくありません。特に部下への育成に熱意のある社員であるほど、その方法に悩んでいる方は多いのではないでしょうか。
しかし、上司と部下がお互いに「パワハラとは何か」を正しく理解することで、必要以上に身構えることなくコミュニケーションを取ることができるようになります。
上司から部下への指導が健全に行われやすくなるため、優秀な人材の育成に期待できるでしょう。
パワハラ研修の種類と内容

「パワハラ」という言葉は既に市民権を得ており、ビジネスパーソンであれば誰もが知っているものですが、どのようなことがパワハラに相当するのかは、グレーゾーンの判断もありジャッジが難しいものも少なくありません。そこでパワハラの中身を確認しておきましょう。
パワハラの判断ポイント
まずパワハラの定義ですが、以下の3つの要件をすべて満たすものと定められています。
【要件】
- 優越的な関係に基づいて(優位性を背景に)行われること
- 業務の適正な範囲を超えて行われること
- 身体的若しくは精神的な苦痛を与えること、又は就業環境を害すること
また、パワハラに当たる行為として代表的なパターンが次の6類型です。ただし、全てのパワハラ行為を網羅したものではないので、これら以外がパワハラに該当しないというわけではありません。
【パワハラ6類型】
- 身体的な攻撃:暴行・障害 など
- 精神的な攻撃:強迫・名誉棄損・侮辱・ひどい暴言 など
- 人間関係からの切り離し:隔離・仲間外し・無視 など
- 過大な要求:業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制・仕事の妨害 など
- 過小な要求:業務上の合理性なく能力や経験と掛け離れた程度の低い仕事を命じることや与えないこと など
- 個の侵害:私的なことに過度に立ち入る など
つまり同じ職場の人に対しての、立場や力関係などを利用した嫌がらせ(業務の範囲を超えていること、相手に精神的な苦痛を与えたり就業環境を悪化させること)の条件が揃った言動がパワハラにあたります。
パワハラは受けた本人が不快に感じただけではパワハラにはならないのですが、受けた本人は不快に感じため「パワハラ」だと主張したり、行為者は「相手のためを思ってしたことだ」と主張するなど見解が食い違うことが多く、判断が難しいものです。
例えば、上司が部下の成長を願って叱咤激励するとします。その叱咤激励を部下が「必要以上に罵倒された」と感じたとしましょう。すると、「パワハラを受けた」として相談が上がることになるのです。パワハラの苦情が出るだけでなく、例え正当な指導であっても、部下が“指導”として受け止められない場合、指導としての効果が期待できなくなってしまうのです。
また同じ言葉を用いたとしても、当事者同士の関係性や表現の仕方によって受け取り方は変わります。そのため「NGワード集」のようなマニュアルも作りづらいのがパワハラの難しいところです。
熱意のある上司が部下にパワハラとして捉えられる可能性があるため、上司は部下への接し方に悩み、本来持っている指導力を発揮できなくなってしまうことも、多くの人事担当者の悩みとなっています。
そのようなケースが出てこないよう、特に力を入れて管理職向け、一般職向けの階層別研修を行う必要のあるハラスメントであると言えるでしょう。
動画研修(eラーニング)で効果的なハラスメント対策を!

ここまでの内容でハラスメント対策が企業にとって必要不可欠なものであることは理解していただけたかと思います。研修実施の方法は大きく分けて「社外研修」「社内研修」そして今主流となりつつある「動画研修(eラーニング)」の3つが挙げられます。
eラーニングのメリット
eラーニング導入で得られるメリットを3つご紹介します。動画だからこそのメリットなので、他の研修方法と比較検討する際の参考にしてみてください。
・時間や場所を選ばずに受講できる
最大のメリットは従業員が業務の合間に受講できるということです。
いざ社外研修や社内研修を実施しようと思うと、受講時間に加えて場所によっては移動時間も発生するため、その分業務に支障が出てしまいます。
時期によっては身を入れて受講しづらい従業員も少なからず出てしまいがちですが、eラーニングであれば自分の業務とのバランスを取りながら受講できるので前向きな姿勢で受けてもらいやすくなります。
・繰り返し受講できる
一斉に受講する機会を用意することはもちろん重要ですが、能動的にパワハラの知識を得たいと思うのは、パワハラに接する何かしら機会があった時です。
例えば「部下を持つことになった」「今日のあの言動はもしかしてパワハラ?」というように当事者になってからの方が当然学習意欲は高まります。
いつでも学ぶ場が用意してあるのはパワハラ対策としても効果的と言えるでしょう。
・研修効果を高められる
動画のeラーニングによって、研修効果をより高めることに期待できます。特にパワハラ研修においては、いかに自分事として捉えられるかが重要です。いつ自分が当事者になるかわからないという緊張感を持ってもらうことが大切です。
動画のeラーニングであれば、事例ドラマを取り入れることで実際のパワハラの場面を再現してリアルにイメージしてもらうことが可能です。受講者にとって印象的な研修となり、研修受講後に似たようなシーンに遭遇した際の行動変容にも期待できる手法であると言えます。
eラーニングのデメリット
eラーニングでの研修実施でデメリットとして挙げられるのは大きく2点です。それぞれについての対処法や解決方法もご紹介します。
・受講率が下がりやすい
モチベーションが従業員によって異なるので、受講を後回しにしてしまう可能性があります。必ず受講してもらえるように呼びかけや、受講状況のチェックをするなど徹底するためには管理する仕組みが必要です。
実施する際には受講率を保つための工夫も一緒に仕組み化しておくのがおすすめです。
・eラーニングの準備にコストがかかる
社内で独自にコンテンツを作成するということも可能ですが、その場合の研修担当者の負担は大きくなります。その他の業務も抱えている状態であれば尚のことです。自社に関するものなどはどうしても自社でコンテンツを作成しなければならないこともありますが、パワハラ研修については既成のものが豊富にあります。
また、パワハラ研修は時代によっても変化する可能性が高いので、アップデートが必要です。専門的な知識を基にしたアップデートを伴う研修なので、長期的な運用を考えても既成コンテンツの活用がおすすめです。
まとめ

パワハラは些細な不注意で誰しもが当事者になりうるものです。最新の正しい知識の伝達と注意喚起をすることで、従業員が安心安全に働ける環境を整備することができます。
パワハラ防止措置が義務付けられている以上パワハラ研修は必須ですが、効果を高めるために、自社に合った、より効果の高い方法を導入することを検討してみてはいかがでしょうか。